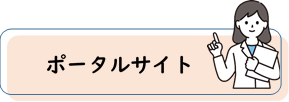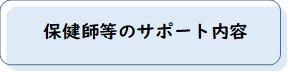健診でわかること(検査項目と基準値)
定められた健診項目(身体測定、血圧測定、血液検査、尿検査、医師の診察、問診)のほかに、市が独自で実施する項目があります。
ここでは検査の目的や基準値について簡単に解説していますので、普段の生活の振り返りや今後の健康づくりにお役立てください。
こんなことがわかります!
肥満かどうかを調べる
身長
身長を計測し 、BMIの算出に使用します。
体重
体重を計測し、BMIの算出に使用します。
BMI(18.5~24.9)
体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) で算出できます。肥満(25.0以上)・やせ(18.5未満)の度合いをみます。
内臓脂肪型肥満かどうかを調べる
腹囲(男性:85cm未満 女性:90cm未満)
へそ周囲径を測ることで、内臓脂肪の面積を推測することができます。内臓脂肪の過剰な蓄積は、糖尿病や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こす原因になります。
高血圧かどうかを調べる
血圧(収縮期:130mmHg未満 拡張期:85mmHg未満)
収縮期(最大)血圧は血液が心臓から送り出されるときの圧力で、拡張期(最小)血圧は血液が心臓に戻るときの血圧です。
血液が流れにくくなるほど、全身に血液を巡らせるために強い圧力をかけなければならなくなります。高血圧の状態が続くと血管壁が障害されて動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳卒中、腎障害のほか心臓に大きな負担がかかるため心肥大を引き起こす要因になります。
脂質代謝を調べる
中性脂肪(空腹時中性脂肪:150mg/dL未満 随時中性脂肪:175mg/dL未満)
中性脂肪は、身体活動のエネルギー源としての役割を持っています。
食事からとったエネルギーが使いきれずに余ると、肝臓で中性脂肪に合成され脂肪組織に蓄えられます。食べ過ぎや飲みすぎ、肥満によって数値が高くなり、動脈硬化を進行させます。
HDLコレステロール(40mg/dL 以上)
血管壁の細胞から余分なコレステロールを肝臓に運び戻す働きをして動脈硬化を防ぐため、「善玉コレステロール」と呼ばれています。
LDLコレステロール(120mg/dL 未満)
LDLが多くなりすぎると血管壁にコレステロールがたまって動脈硬化を促進するため、「悪玉コレステロール」と呼ばれます。
糖代謝を調べる
血糖(空腹時血糖、随時血糖:100mg/dL 未満)
血糖値は、食事や運動などの影響を受けて常に変動しています。空腹時血糖は、10時間以上食事を摂らずに測定した血糖値で、糖尿病や糖尿病予備群の可能性を調べます。血糖値が高い状態が続くと、全身の血管を傷つける原因となり動脈硬化を促進させることにつながります。また、内臓脂肪が多いとインスリンの効き目が悪くなって血糖値が上がってしまいます。
ヘモグロビンA1c(5.6%未満(NGSP値))
検査直前の食事の影響を受けることなく、検査前1~2か月の平均的な血糖値の状態がわかります。
尿糖(-)
尿中に含まれるブドウ糖のことです。血糖値が高くなりすぎると尿にも糖が出るため、糖尿病の進行具合を判断することができます。なお、糖尿病を見つけるには、尿糖より空腹時血糖やHbA1cの値が優先されます。
肝機能を調べる
総蛋白(6.5g/dL ~7.9g/dL)※船橋市独自で実施
血清中に含まれるたんぱくの総量です。 100種類以上のたんぱくがあり、体内で一定になるよう保たれています。 栄養状態や全身状態が悪化すると、血清中のたんぱくの値が変動します。 血清総たんぱくが低い場合は、栄養不良や肝疾患、腎疾患などが疑われます。血清アルブミン(3.9g/dL 以上)※船橋市独自で実施
血清アルブミンは、血清中のたんぱく質の一種で、総たんぱくの約6割を占め、栄養・代謝物質の運搬、浸透圧の維持などの 働きを行います。 栄養状態を評価する際、低栄養に陥っていないかどうかを調べるほか、肝機能を測る指標となるものですAST(GOT)(30U/L以下)
ほとんどが肝細胞に含まれ、この数値が高いとアルコール性肝炎、脂肪肝などの肝臓障害が疑われることがあります。 AST(GOT)は肝臓だけでなく、骨格筋や心臓の筋肉などにも含まれており、ALT(GTP)が高くなく、AST(GOP)のみ高い場合は心筋梗塞や筋肉の病気が疑われます。
ALT(GPT)(30U/L以下)
ほとんどが肝細胞に含まれ、この数値が高いとアルコール性肝炎、脂肪肝などの肝臓障害が疑われることがあります。とくに内臓脂肪型肥満の人は、脂肪肝に注意が必要です。
γーGT(γ―GTP)(50U/L以下)
肝臓や胆道に障害があると数値が高くなるので肝臓障害の発見の手がかりとなります。アルコールによる肝障害の場合に増加が顕著に現れます。
腎臓機能を調べる
尿蛋白(-)
腎臓に異常があると(+)や(++)などになることがあります。たんぱく量が多い場合や持続的にたんぱく尿が認められる場合には、注意が必要です。
血清尿酸(2.1mg/dL~7mg/dL)※船橋市独自で実施
尿酸はプリン体が分解してできた老廃物です。尿酸値が高い状態が続くと、血液に溶けきれない尿酸が結晶化して関節などにたまり、痛風発作を引き起こします。放置すると、発作を繰り返したり尿路結石や腎障害、動脈硬化の原因となります。
血清クレアチニン(男性:1.00mg/dL以下 女性:0.70mg/dL以下 )※船橋市は全員に実施
主に筋肉がたんぱく質をエネルギーとして利用した時にできる老廃物です。腎機能が低下すると数値が高くなり、腎臓の機能障害が考えられます。自覚症状として疲労感やだるさ、体力低下や活力不足を感じたりすることがあります。
尿潜血(-)※船橋市独自で実施
eGFR(60mL/分/1.73㎟以上)※船橋市は全員に実施
貧血かどうかを調べる
白血球数(3100㎟~8400㎟)※船橋市独自で実施
白血球は血液細胞のひとつで、身体を細菌やウイルスなどの異物から守る免疫機能を持ちます。数が多い場合、体内で炎症が起きている可能性があり、細菌感染、心筋梗塞などが疑われます。反対に数が少ない場合は服用中の薬の影響もありますが、骨髄異形成症候群、ウイルス性感染症、再生不良性貧血などの血液疾患の可能性があります。赤血球数(男性:410~530万㎣/ 女性:380~480万 /㎣)※船橋市は全員に実施
赤血球は血液の主成分で、肺から取り込んだ酸素を全身に運ぶ役割を担っています。赤血球数が少ない場合は貧血が疑われ、多すぎる場合は多血症が疑われます。血色素量・ヘマトクリット値とあわせて貧血を調べます。
血色素量(男性:13g/dL 女性:12g/dL )※船橋市は全員に実施
血液中に含まれるヘモグロビンの量を調べます。ヘモグロビンは、赤血球内に存在する鉄を含むたんぱく質で、酸素と結合して全身に運ぶ働きをしています。ヘモグロビンが低い場合は貧血が疑われ、高い場合は多血症や脱水が疑われます。
ヘマトクリット値(男性:39~52% 女性:35~48%)※船橋市は全員に実施
血液中に含まれる赤血球の割合を調べます。ヘマトクリット値が低い場合は貧血が疑われ、ヘマトクリット値が高い場合は多血症が疑われます。
血小板数(14.5万/㎣~32.9万/㎣)※船橋市は全員に実施
詳細な健診
心電図検査※医師の判断で実施
眼底検査※医師の判断で実施
その他
診察(問診)
医師の質問に答えて現在の自分の健康状態(既往歴、自覚症状、他覚症状等)を確認する検査項目です。
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 健康づくり課
-
- 電話 047-409-3404
- FAX 047-409-2934
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日