気付くことが大切
令和8年2月19日
この学校に着任して3年が経とうとしています。何も予定が入っていない限り、できるだけ朝と帰りに校門まで出て、皆さんと挨拶をするようにしています。毎日毎日挨拶を交わしながら一人ひとりを見ていると、ちょっとしたことに感心させられたり、これはどうかなと感じてしまうことがあったりするのです。たかが挨拶と考えがちですが、その日その時の体調や感情、友達との関係やその人の持つ人に対する姿勢などが手に取るようにうかがえるのです。「あれ、今日は少し元気がないな。体調がすぐれないのかな。」とか「表情が硬いな。何かあったのかな。」とか「珍しく元気に挨拶を返してくれたな。何かいいことあったのかな。」などなど・・・。こんなのもあります。「この人といる時は挨拶が返ってくるけど、この人といる時は返ってこないな。」
そして、毎年この季節になると目につくのは人に対する姿勢。寒さが厳しい中、ポケットに手を入れて登校してくる人が目立ちます。ただ、そのような状況の中で、ポケットに手を入れたまま挨拶をして通り過ぎる人と挨拶をする時にはポケットからスッと手を出して挨拶する人がいるのです。「挨拶するだけましだ。」とか「ポケットに手を入れて歩いていること自体、危険だしおかしいじゃないか。」そのような考えももちろんあるでしょう。しかし、人に対する姿勢という点ではどうでしょうか。瞬間的にポケットから手を出して挨拶をする人は、ポケットに手を入れたまま挨拶をすることは、失礼なことだという認識があるのです。誰かに教わったことなのでしょうか。それともその人の持つ感性なのでしょうか。ちょっとしたことなのだけれど、人に対する姿勢という点では感心させられます。何人かの仲間で一緒に登校、下校してくる中でも出す人、出さない人に分かれるのです。挨拶の仕方ひとつでも、その人の人間性が見えてくるものです。気付いていますか。
卒業へのカウントダウン
令和8年2月13日
1、2年生は後期期末テストが終わりました。このあと、3年生にとって中学校生活最後の試練ともいうべき17、18日の公立の学力検査が終わると、学校全体が卒業式に向けて一気に加速し始めます。1、2年生はお世話になった3年生へのはなむけの会として、3年生を送る会の準備を着々と進めていますが、それも最後の仕上げの段階にきていると思います。一人ひとりが精一杯の感謝と激励の想いを3年生に伝えることができるよう、あともう一息、頑張って欲しいと思います。
そのような中で、1、2年生のみなさんに覚えていて欲しいことがあります。それは、みなさんと一緒になって会の準備を進めてくれている学年の先生方は、きっとみなさんの1年後、2年後の姿、そう、送られる立場になったときのみなさんの姿を想像しながら、あれこれとアドバイスしてくれているのです。そこには、「後輩に心から頼りにされ、感謝される3年生になって欲しい」そのような願いもこめられているのです。そのような先生方の想いに応えるためにも、今、一人ひとりが3年生のためにできることを考え、精一杯取り組んで欲しいと思います。1年後、2年後の自分自身の姿に思いを馳せて。今の3年生もそうしてきたように・・・・・。そして3年生は「立つ鳥跡を濁さず」1、2年生の、そしてこれまでみなさんを見守ってくれた学年の先生方の想いに応えることができるよう、残りの学校生活を送って欲しいと思います。
周りが見えていますか
令和8年2月6日
このごろ改めて感じること。早朝、明るくなり始めるのがずいぶん早くなりました。また夕方、5時には日が暮れて真っ暗だったのに、ずいぶん日が長くなったように感じます。ふと周りに目をやると、梅の花が咲き始めていたり、暖かな日差しが差し込んできたり・・・。今朝は、二羽の「めじろ」が仲良く木の枝で羽を休めていました。確実に季節は移り変わり始めていて、春の足音を感じられるようになってきています。みなさん気づいていましたか。ひょっとして気づかずにいたのは私だけでしょうか。
同じように、毎日目にしているものや、特に意識せずに過ごしているものごとに関しては、その変化に気づかず、「改めて見てみると」「言われてみれば」気付くことがよくあります。例えば学年やクラスの仲間については・・・。学校に行けば必ず会える、いつもそこにいる顔ぶれ。いつもと変わらぬ一人ひとり。そう感じているかもしれないけれど、でも、改めてよく見てみると、言われてみれば・・・「そういえば、あの人、夏休み前と比べると随分と落ち着いて見えるなぁ」「あいつ、冬休み明けから考え方や話し方、言葉の使い方が大人になっているような」「言われてみれば、みんな部活動や授業、真剣に打ち込んでいる姿が目立つようになってきたなぁ」どうでしょうか。気付かずにいるのは自分だけで、周りの仲間はどんどんと成長していて・・・あれ、ひょっとして相変わらずなのは自分だけ・・・。そんなことになっていませんか。
人は誰でも「よりよく成長したい」そういう気持ちを持っているものです。知らず知らずのうちに周りの仲間は努力を始めていた。改めて気が付くと自分だけが取り残されて・・・そのようなことにならないように。
初志貫徹
令和8年1月30日
年が明けてから早いもので、1か月がたとうとしています。新年を迎えるにあたって立てた自身の目標、覚えていますか。目標を立てていなかった人も集会などで目標について話があるたびに、ぼんやりと「なりたい自分の姿」がふと頭の中に浮かんだりして、その時は自分自身の新たな可能性を信じて「よし!」という気持ちになっていたのではないかと思います。ですから冬休み明けの集会でみなさん一人ひとりの表情を壇上で見ていて、それぞれにこの先、今よりも更に輝きを放つであろう気配を感じることができました。ところがです。最近のみなさんを見ていると、「あの時感じた輝きはどこに・・・」そう感じてしまう人もちらほらと・・・。
確かに自身で決めた目標達成のために、「継続」して ものごとを行うこと、意志を持ち続けることはそんなに簡単なことではありません。どうしても自分自身の弱さから途中であきらめてしまうこともあると思います。「あの時あきらめずにいたら・・・」「あの時もう少し我慢できていれば・・・」そんな後悔をすること多くないですか。では、「あの時」とはいつなのか。私の経験上、心に決めたものごとを行い始めたとき、乗り越えなければならない「あの時」が何段階かあるように感じます。どういうことか・・・ まず、そのものごとを始めてから3日目。よく三日坊主と言いますよね。まず3日目を乗り越える。次は1週間目。次は2週間目。そして次は1か月。次は3か月。次は半年。半年続けることができれば、そのものごとは自分の中で習慣化されているのではないかと思います。特別な意識をしなくてもできることになっている。つまり目標達成に大きく近づいていると考えていいのではないかと思います。
年が明けて1か月。 「初志貫徹」そのために、もう一度自分自身に気合をいれる。今がその時。ここが「あの時・・・」とならないように。
この時期だからこそ、改めて問うてみます
令和8年1月23日
3年生諸君。朝の会を見ていると全員がしっかりと前を向き、先生方の話に真剣に耳を傾けている姿は大変美しい。人生の岐路とも言うべき受験(検)を控え、教室内に張り詰めた空気が感じられます。ところが、休み時間などを含めた学校生活全体での一人ひとりの姿はどうでしょうか。中には周りの仲間からも伝わる緊張感に堪えきれず、大声、奇声や馬鹿笑いなど、はめをはずしすぎたり、やるべきことが手につかなかったり・・・。今更そんなことで注意を受けている姿を1、2年生が見たらどのように感じるでしょうか。
2年生諸君。来年度、きみたちはこの行田中学校をどのような学校にしたいと考えているのでしょうか。最高学年として、今の3年生が引き継いできた伝統を更に発展させる、そのような思いを持って過ごしているでしょうか。具体的な話をすると、様々な行事を自分たちの力で更に充実したものに とか 部活動では更に上位の成績を とか。前回の話と重なりますが、主体性どころか自主性も感じられず、先生方の指示を受けなければ活動できない、ともすると 3年生が全体の前で注意を受ける、そのような姿を下級生に見せることをどれぐらいの人が情けないことであると感じているでしょうか。
1年生諸君。2か月後には先輩と呼ばれる存在になります。学校生活の細かなきまり、約束事など1年生に質問されてしっかりと答えることができますか。中学生ともなると大人の仲間入りをするようになります。社会一般的なマナーについても守れていますか。例えば、サイレントゾーン、職員室への入り方、廊下・教室での過ごし方、心のこもった挨拶・清掃・歌声などなど。1年生に「先輩、それ違ってませんか。おかしくないですか。」逆に注意されるのではないかと心配になる人、見当たりませんか。
3年生は最高学年と呼ばれるにふさわしい態度を下級生に示せる機会は、あと30日もありません。1、2年生、進級するための準備期間はもう始まっています。再度、自分や自分たちの言動を見直して、他人事ととらえずに自らの手で、自分たちに手で改善していってほしいと思います。
自主性と主体性
令和8年1月15日
学校生活にかかわる様々な場面で、「自主的に」とか「主体的に」という言葉を耳にすることが多くあると思います。「家庭学習に自主的に取り組む」「合唱祭の練習に主体的に取り組む」などなど・・・。「自主的」「主体的」似たような場面で使われることが多いので、みなさん特に区別することなく使っていませんか。「自主性」「主体性」どちらも自ら進んで行動を起こすことを意味しますが、二つの言葉には決定的な違いがあります。「自主性」とはある程度決められたことを誰からの指示がなくても率先して行うことを意味します。これに対して「主体性」とは自らの意志や判断に基づき、自らの責任のもとで行動することを意味します。決められたことや一度教えられたことに対して自ら進んで動くという「自主性」に対して、自分で目標・目的を設定し、課題解決に向けて責任をもって自ら進んで動くという「主体性」。二つにはこのような違いがあるのです。つまり「主体性」は「自主性」の更に上位の性質、行動と言うことができるのではないでしょうか。これは私がみなさんを見ていて感じていることですが、行田中生には「自主性」が身についている生徒は多くいるように感じます。ところが「主体性」となると・・・。言われたこと、指示されたことだけではなく、自ら考え判断して動く。行田中学校を更に活気に満ち溢れた学校へと発展させるためだけではなく、「いじめ」や「SNSを使った誹謗中傷」などを含めた学校生活の陰に潜む様々な課題も、この「主体性」が身についている皆さんであれば解消できるように思うのです。
七草 若菜摘み
令和8年1月8日
2026年、新しい年が始まりました。6日の集会でのみなさんの顔を見て、休み中、大きな事故なく無事に過ごせていたことにホッとしました。「1年の計は元旦にあり」自分の心の中で立てた計画、目標をしっかりと実行、達成できるよう日々努力していきましょう。
さて、昨日は1月7日。七草です。お正月におせち料理などのごちそうを食べすぎて疲れたおなかの調子を整え、今年1年の無病息災を願い七草粥を食べるという風習です。
ところで、この風習の起源ですが・・・ 1月7日は「人日(じんじつ)の節句」という桃の節句や端午の節句と並ぶ五節句のひとつです。この日に古代中国では七種の菜の煮物や汁物を食べ、無病息災を願ったそうです。一方、日本ではお正月に野原の若菜を摘んで食べる「若菜摘み」(新春に若菜を食べると邪気を払って病気が退散すると考えられていました。) という風習と1月15日に七種の穀物でつくったお粥を食べて五穀豊穣を願う朝廷行事があったそうです。中国の「人日の節句」と日本のお正月の風習が合わさって、7日の節句に七草粥を食べるようになったといわれています。
では、七草とは・・・言えますか。「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すすしろ」春の七草です。「秋の七草」もあります。調べてみてください。ちなみに・・・百人一首に「君がため 春の野に出でて 若菜摘む わが衣手に 雪は降りつつ」という歌がありますよね。正月の「若菜摘み」という風習が歌われています。
失われつつある日本の文化、風習、年中行事などにも是非、目を向けてみてください。
心をこめて清掃している姿とは・・・
令和7年12月19日
「心のこもった挨拶 清掃 歌声」みなさんそれぞれに、普段から意識して生活してくれていると思います。その中で「清掃」については今ひとつと感じることが・・・ 友達と喋りながら とか、ごみの取り忘れがあったり とか、清掃用具の片づけ忘れがあったりなど目にすることがしばしばあります。そのような中、12月に入ってから3年生は給食後に下校することが多くなり、職員室前の廊下や職員玄関などの3年生の清掃分担場所には、清掃の時間に人が来なくなりました。ところがです。ここのところ、二人の生徒が黙々と職員室前の廊下を水拭きで拭き進めてくるのを目にするようになりました。その姿たるや、自分の顔が廊下に映るほどの力強さで、しかも素早く拭き進めてくるのです。「心のこもった清掃」表現の仕方としては「心をこめて清掃」ですね。この美しい姿勢こそが「心をこめて清掃」している姿だと感じました。以前、この紙面の「創立50周年によせて(2)」で、「今の行田中のこの整った環境を乱すことなく、次の代へと引き継いでいかなければならない」という話をしましたね。できれば、さらに磨きをかけた状態で次の世代に引き渡してほしい。そこに「心をこめる」意義を見出してほしいと思います。「心をこめて清掃」している姿とは・・・喋らず黙々と そこにあるものは動かして掃く、拭く 自分で仕事を探す やり残しがないか隅々を確認する 道具は元あった場所へ、次の人が使いやすいように整理整頓を心がける。リーダーを中心にお互い声掛けを。
因果応報
令和7年12月12日
友達から次のようなライン(メール)が届きました。よほど急いでいたのか漢字の変換もそこそこで、読点(、)もありません。
(1)その場所ではきものを脱ぐんだよ!
(2)お母さんはイライラして電話をかけてきた私を怒鳴ったんだよ。
あなたはこの文章をどう読みますか。読点(、)を適当な場所に入れて読んでみてください。
(1)その場所では、着物を脱ぐんだよ!
(2)お母さんはイライラして、電話をかけてきた私を怒鳴ったんだよ。
どうですか。このように読んだ人いませんか。このように読点を入れて読んでしまうと、
(1)について・・・その場で裸になってしまう。
(2)について・・・とんでもないお母さんだという印象をもってしまう。
ところがです。本当に伝えたかったのは・・・
(1)その場所で、はき物を脱ぐんだよ!
(2)お母さんは、イライラして電話をかけてきた私を怒鳴ったんだよ。
今回は自分がライン(メール)を受け取った側としましたが、自分が送信していた側だとすると・・・相手に恥をかかせてしまう、ある人に対して間違った印象を与えてしまうことになります。どうですか。同じようなことを経験したことありませんか。そんな意味で送信したつもりではなかったのに・・・とか、それがもとで送信した相手とトラブルになってしまったり・・・とか。
SNSの利用の仕方についてはとても注意が必要です。普段、何気なく使用しているライン(メール)においても、この例のように気を付けなければトラブルに発展するケースも多々あります。大切な内容は、直接会って言葉を交わして伝える。いらぬトラブルを避るためにも・・・。まして、わざと人をおとしめるような使い方はしないように。いつかわが身に返ってきます。
行中フェス(笑顔満祭 )に想う・・・
令和7年12月5日
明日は午前中に授業参観。午後は行田中フェスティバルが予定されています。1組のみなさんは、ふなっ子バザールという大きなイベントを控えています。1組のみなさんは、ここまでの準備が本当に大変だったと思います。行田中フェスティバルに参加できないのは残念だけど、一生懸命につくった物品の販売を通して、たくさんの方々と触れ合うことを存分に楽しんできてください。
さて、行中フェスですが、サブタイトルを知っていますか。笑顔満載の「載」を「まつり」という漢字に変換して、「笑顔満祭」としています。「あふれんばかりの笑顔でいっぱいのお祭りになるように」との願いからつけられたサブタイトルです。果たして誰の笑顔を想い描いてこのサブタイトルはつけられたのでしょうか・・・。わかりますか。 それは行田中生徒の、つまりはきみたち一人ひとりの笑顔を想いながらつけられたサブタイトルなのです。
では、誰がきみたちの笑顔を想っているのでしょうか。それは本校のSTSの方々です。本校はPTAという組織ではなく、地域の方と保護者で組織する「STS(Student.Teacher.Supporter)」という組織が先生やみなさんの学校生活を応援し、支えてくれています。その方々がこの行中フェスを企画、運営してくれているのです。ことの起こりは3年前です。我々の記憶からも遠い昔のことのように薄れてしまっている「新型コロナウイルス感染症」。通常の生活に戻りはしたけれど、様々なイベントが中止になった時期があったと思います。そんな中を過ごしてきた生徒のために、「みんなが笑顔になる企画を」とSTSの方々が立ち上がって始めてくださったのがこの行中フェスです。本当にありがたいことです。
そこでひとつ、みなさんに問うてみたいことがあります。今の行田中学校は、一人ひとりが安全・安心に過ごすことができる、STSの方々が想う「あふれんばかりの笑顔いっぱい」の学校生活を送ることができる、そのような環境でしょうか。どうですか。この学校で過ごすみなさん一人ひとりが「今、自分はどのような行動をとるべきなのか」都度、誰かの考えに流されるのではなく、自分自身の心の中にある「正義」に照らし合わせて考え、行動することができていますか。
STSの方々の想いやご苦労に応えることができている一人ひとりですか。
締めくくりを大切に
令和7年11月27日
ふと気が付けば11月もあと数日。来週には12月を迎えます。月ごとのカレンダーだと今年の分はあと一枚。2025年も終盤に近付いてきています。あと1週間もすると「師走」という言葉があちらこちらから聞こえ始め、世の中全体がなんとなく慌ただしくなってきます。みなさんにとっても今週でテストが終わり、あとはクリスマスやお正月という楽しみなイベントが控えている冬休みを迎えるだけとなり、どことなく気分がうきうき、そわそわする時期になってきます。そのような中でも、周りの雰囲気にただただ流されて過ごすのではなく、物事にけじめをしっかりつけて、自分らしい1年の締めくくりができるようにしたいものです。
そこで、みなさんに改めて問うてみます。2025年を迎えるにあたって自分自身が立てた「1年間の目標」覚えていますか。4月に新しい「年度」を迎えるにあたって立てた、学校生活での目標とは別に、今年の1月1日、新しい年を迎えるにあたり誓った思いです。はっきりと言葉にはしていない人も、「今年はこんな年に」と思い描いた内容があったのではないかと思います。「思い」を実行することはできましたか。実行できていない人、今年はまだひと月あります。思いを実行するための時間はまだまだ十分あります。2026年を今年よりも更に良い年にするためにも、この締めくくりの1か月を大切に。
一人一人を大切に・・・
令和7年11月21日
大きな盛り上がりを見せた合唱祭も終わりました。賞を取ったクラスも残念ながら賞に入らなかったクラスもそれぞれに達成感や充実感、満足感を感じることができたのではないかと思います。結果よりもその過程が大切。どのクラスも当日を迎えるまでの道のりで、様々な課題を乗り越えてきたことと思います。その経験を大切に今後の学校生活に生かせるようにしてほしいと思います。
では、具体的に「その経験を学校生活に生かす」とは・・・合唱祭だけではなく、体育祭の取り組みでもそうだったと思うのですが、「賞を取りたい」「一番になりたい」そう思って練習に取り組んだ人が多いと思います。でもそれは、自分一人では成し遂げられないものです。また、気の合う仲間だけを集めて頑張ってもその思いには届かないと思います。なぜならクラス全員での取り組みなのですから・・・。気の合う人も、そうではない人も、あまり話をしたことのない人も全て含めて、クラス全員の力を結集しないと成し遂げられないことです。合唱祭での講師の先生の講評にもありましたが、「一人一人を大切にする心」が大切なのです。今回の合唱においても、特に表現力をつけていく段階では、クラス全員の心が一つになった時の力を感じることがあったのではないかと思います。「一人ひとりを大切にする」雰囲気、皆さんの学級では育ってきているでしょうか。自分自身にはそのような心が育ってきていますか。なんとなく気が合わない、気に入らないからといって何人かで悪口や嫌味を言ったり、誰かを仲間外れにする。皆さんを見ていて、そのような雰囲気を感じる時があります。ほんのひと握りの人たちなのですが・・・。そのようなことをしているようではここまでの取り組みも水の泡・・・。クラスの雰囲気や自分自身の言動を振り返り、考えてみてください。
心のこもった歌声
令和7年11月13日
いよいよ間近に迫ってきました。合唱祭。音楽の授業、昼休み、放課後と、心地よい歌声がここそこから聴こえてきます。どのクラスも最後の仕上げに余念なく取り組んでいる様子がうかがえます。
先日行われた各学年のリハーサル。今年は全学年、全クラスの合唱を聴くことができました。リハーサルの段階ではボリュームや各パートのバランス、歌詞の明瞭さなど、それぞれにまだまだ課題があるように感じました。音程をとって歌うことで精一杯で、それぞれのクラスの色や歌詞への思いを伝えきれておらず、「心のこもった歌声」にはもう少し・・・という感じでした。学年主任の先生方からも、今日の反省を生かして、1週間以上あるここからの取り組みが大切。ただ歌うだけではなく、それぞれのクラス、歌詞への思いをもっともっと表現できるように。そのような話があったと思います。ここ数日、どのクラスも紆余曲折はあったことと思いますが、音程をとるだけの歌声から、少しずつ変化していきているように感じます。美しさだけではなく・・・。
「心のこもった」「表現力豊かな」歌声は聴く人に心地よさを与えてくれます。感動を与えてくれます。それはきっと、歌っている一人ひとりがそこにいることに心地よさを感じているから。一人ひとりが自分自身の音色を重ねることができているから。一人ひとりが クラスの思いを歌詞にのせて伝えることができているから。
「心のこもった」「表現力豊かな」歌声 ・・・一人ひとりを大切にできているクラスであるからこそ、成し遂げることができるのだと思います。
行田中生の良いところ
令和7年11月7日
50周年の記念式典お疲れさまでした。厳粛な雰囲気の中、しっかりとした態度で式に臨めていたように感じます。式辞の中でもお話ししましたが、50周年という記念すべき特別な年に在校していることを、素晴らしい思い出として心に刻んで欲しいと思います。
さて、その50周年の式典とは打って変わって、とても盛り上がった午後の芸術鑑賞会。全員参加型の内容で、一人一人本当に楽しんでいる姿が印象的でした。最後は行中フェスティバル同様、音楽に全身で反応して、舞台すれすれまで全員が押し寄せて飛んだり跳ねたりと大盛り上がりでした。普通ならこの後、収集がつかなくなって大変ことになることが予想されますが、行田中の先生方は何一つ心配していませんでした。なぜなら、このあと静かにするべきところはしっかりとけじめをつけて行動できるキミたちを知っているからです。案の定、司会の方の「では、元の状態に戻ってください」のひと言で、潮が引くかのように元の状態に整列し、黙って次の話を聞くキミたちがそこにいました。そんなキミたちを先生方はとても誇らしく思っています。『ハッピーフレンズ』の方々も「盛り上げるところは盛り上げてくれて、聞くところはしっかりと聞いてくれる。とても素晴らしい生徒さんたちで、とてもやりやすくて我々もいつも以上にのりのりでできました。今年一番の学校です。」と褒めていただきました。キミたちのとても良いところ、このまま失くさずに。
創立50周年によせて(3)
令和7年10月28日
今回は校歌と校章についてです。
本校の校歌ですが、独特の歌詞であるように感じますよね。この校歌を作詩してくださった人は「斎藤信夫さん」という方です。実はこの方、ある有名な歌を作詩している方なのです。「♪しずかな しずかな 里の秋♪」聞いたことありますよね。小学校の音楽の教科書に長年採用され、「日本の歌百選」にも選ばれている「里の秋」を作詩した方なのです。そのことを知ると、この独特の歌詞にも「なるほどな」とうなずけるところがありますよね。
次に校章です。本校の校章はシンボルツリーの銀杏を図案化したものです。3枚の銀杏の葉と全体を円でモチーフしているそうです。「円」は円満な人格を、3つの葉は校訓とも言うべき、目指す生徒像「敬愛」「創造」「躍進」をあらわしたものだそうです。現在は制服に校章をつけてはいませんが、旧制服では制服に校章をつけていました。最近では身に着けることもなくなり、目にする機会も少なくなりましたが、行田中生ならば校章は何をモチーフしたものなのか、その由来は、これぐらいは知っておくべきですよね。
校歌、校章については職員玄関に校歌の直筆譜と校章の原画が掲示してあります。
創立50周年によせて(2)
令和7年10月23日
前回の内容から、大廊下の写真を見てくれましたか。現在の行田中学校の校庭の様子とはずいぶん違うことがわかったと思います。校庭やグランドの状況がいかに整っていなかったかというと、校舎が当時としては明るくモダンであったがゆえに、廃棄物がそのままに残り、草木も植えられていない、赤土むき出しの状況であった校庭やグランドの方がかえってひどく目立ってしまっていたそうです。近隣に住む方々も、「当時の行田中はほとんど整地がされておらず、赤土がむき出しで、ひとたび風がふくと砂埃がひどかった」と話していました。また、近隣の方を悩ませたのは晴天時の風ですが、当時の先生や生徒を悩ませたのが雨だそうです。そのようなグランドですから水はけが悪く、ひと雨降るとあちらこちらに水たまりができ、1週間は使用できない状況が続いたそうです。
では、そのような状況からどのようにして現在のような緑の多い校庭、水はけの良いグランドへと変化を遂げてきたのでしょうか。業者にお願いするだけではなく、当時の先生や生徒が植樹作業、校庭の整地、あちこちに残っている廃棄物の除去作業、グランドつくりを連日行ったのだそうです。きっと、近い未来には、行田中が現在のような整った環境になるであろうことを夢見て、次の代へと望みを託しながら・・・。50周年を機に、そのような先人の努力のおかげで私たちは今、このような整った環境の中で生活できているということを改めて知ってほしいと思います。そしてこの環境を乱すことなく、次の代へと引き継いでいかなければならないことも・・・・・。
創立50周年によせて(1)
令和7年10月16日
今月の31日に創立50周年の式典が行われます。50周年を迎えるこの年に行田中生としてここにいること、これも何かの縁ですね。何年、何十年か後に「そういえば行田中の50周年の年に行田中にいたんだよなぁ」そんな風に思い出す時が来ると思います。ひと口に50周年というけれど、言い換えれば半世紀です。この地域をそして日本社会を支える人材を半世紀もの間、育んできたのです。その数なんと12,915人。12,915人 もの生徒が行田中学校の門をくぐり、卒業生として羽ばたいていきました。そのような「地域の宝」ともいうべき行田中学校の功績をたたえ、是非みなさんも、地域の方と一緒に50周年をお祝いしてあげてほしいと思います。
50周年を迎えるにあたり何回かに分けて、少し行田中学校の歴史に触れてみたいと思います。まず開校当時の話です。行田中学校は昭和51年に、海神中、葛飾中、法田中の生徒が増加傾向にあり、このままでは教室が足りなくなってしまうため、新たに学区を設けて創設され学校です。開校当時は生徒数239名の7学級、教職員数18名でした。さて、現在は?というと生徒数915名の29学級、教職員数68名というとても大きな学校です。開校当時は校庭の整地も完全ではなく、それまで使用していた道路が校庭に残ったままになっていたそうです。(大廊下に写真があります。是非ご覧ください)・・・次回に続く。
駅伝の壮行会にて・・・
令和7年10月10日
いよいよです。船橋市総合体育大会の最後に行われる種目「駅伝の部」。明日(10月11日)運動公園陸上競技場を中心に運動公園内の周回コースを走ります。女子9時20分、男子10時30分スタートです。6月に総合体育大会の壮行会を行って随分月日が経っているので、改めて今日、駅伝選手の壮行会を行いました。選手のみなさんは、全校生徒からの応援の拍手を胸に、学校代表としてベストを尽くしてほしいと思います。
さて、今日、壮行会に集まった皆さんを見て、学校全体で「一つひとつの取り組み(今回は駅伝)」を盛り上げていけるこの雰囲気が「とてもいいな」と感じました。きっとみなさんの学校生活全般に落ち着きが見られるからこそ、このような雰囲気づくりができるのだと思います。どういうことかというと・・・おそらく、学校全体が俗にいう「荒れた」状態であると、全体を一堂に会するとなると時間がかかる、騒がしくなる、当然先生が叱ることも増える。ならば極力、全体を集めずに物事を済まそう。これでは「一つひとつの取り組み」で学校全体が盛り上がる雰囲気を味わうことは難しくなります。 では本校は?というと・・・これだけの人数がいるにもかかわらず、短時間で静かに集まり、そして先生方が余計な注意をすることもなく「会」そのものを盛り上げることができる。そのようなみなさんだからこそ、先生方も全校生徒が一堂に会しての駅伝選手壮行会を計画することができるのです。きっと選手もみなさんからパワーをもらったことと思います。今後もこの雰囲気を大切にしてほしいとつくづく感じました。
「創造」「躍進」
令和7年10月2日
夏休み明けから続いた体育祭練習。毎日毎時間、グラウンドから元気な声が聞こえていたのですが 、体育祭の終了とともに平静を取り戻したように静まり返り、それに代わって今はクラスごとに各パートの歌声が校舎内に響いています。歌詞に思いを馳せながら、段階的に合唱を創り上げている様子がうかがえます。また、登校時間には生徒会役員選挙立候補者の挨拶運動が始まっています。「おはようございます!」正門や昇降口前で一ひとりに清き一票を訴える声には、主体性、積極性はもちろん、それぞれの選挙公約に 「この学校をより良くするためにはここをこうするべき」という発想力を感じ取ることができます。
ところで・・・「敬愛・創造・躍進」校訓ともいえる目指す生徒像。「創造」・・・発想豊かに創意工夫する生徒。「躍進」・・・主体的、積極的に生きるたくましい生徒。合唱祭の取り組みに例えるなら、聞いている人の心に響く合唱をつくりあげていくためには、クラス独自のハーモニーを創意工夫し表現する力が必要。また体育祭もそうでしたが、合唱祭も一人ひとりが自分自身にできることを考えて主体的、積極的に関わる態度が大切。一人ひとり充実した時間を過ごすことができた体育祭同様、この機に生徒会役員選挙に立候補している皆さんにならって「創造」「躍進」意識してみてください。
体育祭によせて
令和7年9月25日
いよいよ明日です。学校行事の中でも大いに盛り上がりが期待できる体育祭。運動の得意な人もそうでない人も、集団での取り組みに積極的な人もそうでない人も、それぞれの得意とするところや自分自身にできることなどをとおして体育祭にかかわって欲しい。誰もがみんな持っている自分自身の才能をこの体育祭の中で生かしてほしい、一人ひとり様々な形で輝ける場面がきっとあるはずだよ、 そのような思いが本年度の体育祭のスローガン「百花繚乱~咲き誇れ、それぞれの色で~」に込められていると思います。明日の体育祭では一人一人の持つ色(才能)を存分に輝かせることはもちろん、全体として調和のとれた鮮やかな色の花を校庭いっぱいに咲かせてほしいと願っています。
「一人一人の持つ色(才能)を」・・・ある人は競技の中で、ある人はそれを支える側で、ある人は声援などで全体を盛り上げることで、ある人は任された役割を頑張ることで、ある人は実行委員などに協力することで・・・それぞれに放つことができる輝きがあると思います。是非、一人一人の持つ色(才能)を輝かせてほしいと思います。
「全体として調和のとれた鮮やかな色の花を」・・・個々に持つ色(才能)を結集して、1年生、2年生、3年生、それぞれの学年にふさわしい取り組みをお願いします。きみたちだけでなく先生方や保護者、地域の方も含めてそこに集うみんなの笑顔が輝く、色鮮やかな思い出の1ページをみんなの力でつくりあげてほしいと思います。
暑さ寒さも彼岸まで・・・
令和7年9月19日
彼岸とは春分の日、秋分の日を中日とし、前後3日間を合わせた7日間をいいます。お墓参りに行く人も多いのではないでしょうか。秋の彼岸の入りは9月20日。「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、彼岸の入りを前にして今日はとても過ごしやすい秋らしい気候になりました。春の彼岸の頃は寒さがやわらぎ、穏やかで暖かな気候への移り変わりを感じることができます。どちらもこれまでの暑さや寒さが嘘のように感じられ、どことなくホッとする陽気に、人の様子にも多かれ少なかれ変化が見て取れるのは気のせいでしょうか。春分は厳しい寒さによって知らず知らずのうちに力が入っていた肩の力が抜けて穏やかさを取り戻し、秋分は厳しい暑さで疲労感が漂っていた頭と体が精気を取り戻す。今日はなんとなく様々な物事にやる気が湧いてきた。そんな感じがしませんか。何をするにせよ集中して取り組むことができる良い季節です。夏休み明けみなさんに「自治活動の活性化」を課題として掲げました。まずは体育祭の成功に向けて、実行委員を中心に昨年よりレベルアップした取り組みとなるよう、一人一人が「自治」を意識して活動してくれることを期待しているのですが、さて、6時間目の全体練習はどうであったでしょうか。各学年、それぞれにふさわしい言動がとれていたでしょうか。
夏休み明けの様子
令和7年9月11日
夏休み明け、あれよあれよという間に期末テストが始まりました。事前の計画から試験勉強としっかり取り組むことはできたでしょうか。まだまだ夏休み気分が抜けず、夢の中にいるような感じでテストの2日間が過ぎてしまった人はいないでしょうか。ほとんどの人は大丈夫だとは思いますが、中には・・・・・。
さて、夏休み明けのみなさんの様子を見ていて感じたこと・・・・・。
1年生。挨拶の仕方がとても良くなりました。もとから元気に挨拶できる人が多かったのですが、しっかり相手の目を見て、自分から挨拶できる人がとても多くなりました。部活動やクラスで取り組んでいるのでしょうか?とてもすがすがしい気持ちになります。ただ、行動を共にしている集団によって差が感じられるのは気のせいでしょうか?
2年生。先輩としての自覚のあらわれでしょうか?休み時間の過ごし方やものごとに取り組む姿勢に、落ち着きと思慮深さが見られるようになりました。ただし個人差がありますね。自覚が感じられる人とそうではない人と・・・・・。さて自分はどちらでしょうか?先生だけではなく、後輩はきみたち一人ひとりをよ~く見ていますよ。
3年生。夏休み中、自身の進路について具体的に動き始めたこともあり、一人ひとり顔つきが大人びてきたように感じます。実力テスト、定期テストとその真剣な表情と取り組みには、「さすが3年生」全体的にそのような雰囲気を感じます。
再会 再開
令和7年9月1日
長かった夏休みも終わり、校舎内にみなさんの元気な声が戻ってきました。休み中の校舎内はというと、シーンと静まり返っていて、先生方のかすかな話し声と足音だけしかしない、どこか空虚さを感じざるを得ない雰囲気でした。ところが今日は校内のここそこで聞こえるみなさんの声、活動している姿を感じることができ、夏休み中はただのコンクリートの塊にしか感じなかった校舎が、生き物のように息を吹き返した、そんな感じがしました。夏休み明け、再びみなさんの元気な姿に会えてほっとしています。
さて、今日の集会でも話をしましたが、まずは夏休み中、個々に蓄えた力をこれからの学校生活に生かしてほしいと思います。特に自治活動に焦点を当て、自分たちの手でより良いものを作り上げていこうとする雰囲気を大切に。体育祭や合唱祭などの行事や生徒会活動、部活動などをとおして集団としての力を高めていこう。自身の役割を自覚し遂行する。先輩として後輩を正しい方向に導いていく。そのような姿勢を大切に夏休み後の学校生活を送っていきましょう。
有意義に
令和7年7月18日
明日から(正確に言うと21日から)夏休みに入ります。今日の集会で自分自身が決めた「この夏休み絶対にこれだけは」必ず実行してください。まさか、もう忘れてしまったという人いませんよね。夏休み明け、一人一人にどうであったか聞くかもしれません。
(このように表現したときは必ず聞くと思っていてください。) さて、これから夏休みということで、新年度が始まってからの学校生活に一区切りがつきます。この夏休みが学校生活における一つの節目です。節目節目を大切にしてほしいという話は以前したことがありますね。この夏休みをどのように過ごすかによって、それぞれに成長の度合いが変わってきます。そこで、夏休み中、自身で立てた計画に従って過ごす中で「休憩時間」や「自由時間」が必ずあると思います。そのような時間に是非一度、4月からの自身の学校生活を振り返ってみてください。 できればこの「校長室から」を読み返しながら・・・この機会に自分自身の言動を振り返ることができる人は、心に余裕がある人。自分自身の心に磨きをかけられる人。きっと有意義な夏休みを送ることができると思います。有意義とは「意味・価値があると考えられること 」 9月になって夏休みの生活を振り返った時、意味、価値を見出せる44日間を送ってください。
ん・・・絶句
令和7年7月10日
昨日の一斉下校中のことです。オレンジ色のごみ収集車が保健室の横に止まっていました。もちろんその車を操作して働いている人もその場にいました。その横を通るなり「くせーっ!」そう叫ぶ声を耳にしました。職員玄関に通じる階段を降りながら・・・校門で皆さんを見送りながら・・・一人ではなく何名かです。一斉にたくさんの人が流れに沿って下校していたので、誰ということは特定できませんでした。
さて、みなさん、どう思いますか。
(1)集めているのはこの学校から出たものです。この学校から出たもの、つまりは皆さんが出したものです。
(2)世のため、人のためにと働いてくれている人たちです。中にはコロナ禍で大変だった時も、感染覚悟でこの仕事をしてくれていた人も
います。誰もができることではありません。 その職に誇りを持って働いている人たちです。
(3)知り合いや家族がそのような職業に就いている仲間が身の回りにいるかもしれません。
中学生相手にこのような話をしなければならないとは・・・ しかも自分が勤めている学校の生徒にです。人として、本来どのような言葉がけをするべきなのでしょうか。 情けない。絶句です。
行田中生としての自覚をもって・・・
令和7年7月2日
みなさんの下校時の様子や放課後の過ごし方について、近隣にお住まいの方から苦言を呈されることがしばらく続いたのですが、先日、とてもうれしいことに「とても感心した」というお電話がありました。是非、校長先生にも聞いて欲しいと・・・。
その内容は・・・その人は自家用車で通勤していて、学校周辺の道を車で通って帰宅しているのだそうです。つい先日の夕方、いつもの通り車で帰宅していると、いつもは見かけないほどの人数で行田中の生徒が下校していたそうです。その時の道路を歩く様子が、かなりの人数で歩いているにもかかわらず、車の通行の妨げになることもなく、歩道からはみ出さないよう整然と歩いているのでその姿にとても感心した、というものでした。
私もそうですが、先生方も皆さんの行いが褒められたり、良い評価を聞いたりすると、とてもうれしい気持ちになります。ただ、悪いうわさというものは、たまたま一度だけのことであっても あっ! という間に広まります。しかし、良いうわさというものは、一度だけではなかなか・・・。「行田中生としての自覚をもって」よくそのように言いますけど、一人一人の行いが行田中学校の生徒の良いうわさにも悪いうわさにもつながるのです・・・。今日も整列下校ですね。
思いを一つに
令和7年6月25日
さて、今週末からいよいよ夏季総合体育大会が始まります。3年生にとっては3年間の集大成とも言える大会です。また、文化部も3年生最後の発表会、コンクールが控えています。是非、悔いの残らないよう、最高のパフォーマンスを発揮できるよう心身ともに準備を整えてください。
ところで「悔いの残らないように」ひとことで簡単に言ってしまうけど、どのような状態、状況が「悔いが残ってしまう」状態、状況なのか。その日の好不調やけがなどにより思うような結果につながらなかった。それも一つかもしれませんが、特に3年生は、これまで多くの時間を共に積み重ねてきた仲間と「思いを一つにして」大会や発表会、コンクールに臨むことができないことほど「悔いが残ってしまうことはない」と思うのです。全ての3年生が試合に出られるわけではありません。控えの選手として大会に参加する3年生もいるでしょう。発表会、コンクールも全ての3年生が自分が望んでいた役割で参加できるわけではありません。でも、ここまでチーム内で競い合いながらお互いを高め合ってきた仲間であるならば、例えサポートする側になっても、思い描いていたような役割ではなくても、自分の出番ではなくても、互いに思いは一つであるはずです。是非、思いを一つにチーム一丸となって大会に臨んでください。
また、1・2年生は3年生をしっかりとサポートすること。3年生が大会や発表会、コンクールに集中して、全力を注ぐことができるような心配りをお願いします。特に2年生。この大会でのサポートの仕方を1年生は見ています。自分たちが3年生になった時のことを考えて、今の1年生にしっかりサポートの仕方を教えてあげてください。一番大切なことは、3年生と同じ気持ちで大会、発表会、コンクールに臨むことです。
安心して過ごすことができる学校とは・・・
令和7年6月19日
突然ですが、みなさんにとって「安心して過ごすことができる学校」とはどのような学校ですか。パッと思い浮かぶのが「いじめや暴力のない学校」だと思います。ただ、いじめや暴力はいけないことであり、そのようなことがなければみんなが過ごしやすいことはわかっているのだけれど、例えばいじめについてならば「いかなる理由があってもいじめはいけないことなのだ」「そのような行為がいじめに発展していくのではないのか」「その行為は弱い者いじめと同じなのではないか」と自分の考えや思いを率直に言える仲間関係でなければ、いじめはなくならないと思うのです。そう考えると、自分の心の中にある「正義感」からくる考えや思いを率直に口にすることができる雰囲気であること、これも「安心して過ごすことができる学校」の条件の一つとしてあげられるのではないでしょうか。「こんなこと言ったら何か言われそう・・・」そのようなことを考えてしまって、自分の考えや思いを口に出すことをためらってしまう。びくびくと周りを気にしてしまう自分がいる。そのような雰囲気であっては決して「安心して過ごすことができる学校」とは言えないと思います。 これは私の考える「安心して過ごすことのできる学校」の条件です。みなさんの考える「安心して過ごすことができる学校」とは・・・
SNSやネットの問題
令和7年6月11日
行田中学校だけではなく、今、ほとんどの学校で必ずと言っていいほど、生活指導上の問題で話題にあがることがらと言えば・・・SNSやネットによるトラブル。みなさんも自分の身近でトラブルを耳にしたことがあると思います。特に他人の個人情報や写真などの取り扱いについては、悪意がなくても本人の承諾なくして勝手に取り扱ってはいけないことは知っていると思います。場合によっては刑罰をうけるようなことになってしまう場合も・・・。でも、どういうわけかあとを絶たないのですよ、SNSやネットによるトラブルが。そこで、何人かの2年生にSNSやネットによるトラブルについていくつかの質問をしてみたところ、とても参考になる答えが返ってきたのでみなさんに伝えたいと思います。
〇悪いことだとわかっているのになぜ次々と起こるのか。
周りにあおられてウケねらいや怒りにまかせて、後先を考えずにその場の勢いでやってしまうことが多いから。
〇自分自身、どのように行動したらそのようなことを防ぐことができるか。
自分が行動を起こす前に少し間をおいて、やって良いことなのか悪いことなのかをしっかり考える。こんなことを言ったら、言わ
れた方はどう感じるか。こんなことをしてしまったら、その後どんなことになるか。など・・・
〇もしSNSやネットに自分や友達の個人情報が載せられていることを知ったらどうするか。
その内容を友達に知らせる前に、まずは身近な大人(保護者や先生など)に相談する。(友達にその内容を送ることで、新たな拡散に
つながる可能性があるから)
どうですか。自分自身がトラブルの発信源にならないようにするだけではなく、拡散を防ぐことにもつながる内容です。是非参考に。
あなたの「頭や心のもやもや」を晴らす方法は・・・
令和7年6月4日
見たくも、聞きたくもないだろうけど、今日の話題としてどうしても触れなければならないので、あえて書かせてもらいます。 「中間テスト1週間前」 寝ても覚めても頭の片隅にずーっとひっかかっていて、どうしたら忘れられるのか。いや、忘れてしまっては困るのです。かと言って、やらなければならないことはわかっているのだけどなかなか・・・。そんなモヤモヤした気持ちでいるのは自分だけではなく、この期間はみんな同じ気持ちでいるのですよ。大声を出したくなったり、意味もなく暴れたくなったり、やけになったり、落ち込んだり・・・。そんな人、最近よく見かけませんか。テスト前などもそうですが、人は極度の緊張状態が続くとその緊張状態から逃れたいがため、その場しのぎの普段はとらない行動をとってしまったりするものです。衝動的に大声や奇声をあげたり、意味もなく暴れたり・・・。このような行動をとってしまうと、テスト明けにきっと後悔することになります。誰にも迷惑をかけずに緊張状態(気分)を晴らす、自分なりの方法を持っていますか。
慣れる 馴れる
令和7年5月30日
来週からは6月。前々回の校長室からで、「ものは考えよう、まだまだ始まったばかり」という話をしましたが、気持ちを入れなおすことができましたか。今日はこの2か月について、少し違う観点からの話をします。
1年生は中学校生活になれましたか。2、3年生もそれぞれに迎えた新しい環境、立場になれましたか。「なれましたか」なぜひらがななのか。「なれる」という言葉を用いるとき、「慣れる」「馴れる」二つ表記の仕方があることを知っていますか。今の自分にはどちらの漢字を使うのが適当か・・・。
一つ目の「慣れる」は経験を重ねて当たり前になること・上手になること。二つ目の「馴れる」は人に対して警戒心がなくなること・親しみを持つこと。「なれなれしい」という言葉を用いるときは、「馴れ馴れしい」と書きます。親しみを持てるようになることは良いことだけど、「親しき中にも礼儀あり」最低限の礼儀、マナー、ルールを守ってこその集団生活です。さて、様々なことに「なれはじめた」今の自分、どちらの漢字が当てはまりますか。
くどいようだけど・・・
令和7年5月20日
この前の全校集会でも話をした内容です。くどいようだけどわかるまで、できるまで言い続けます。「サイレントゾーンを含めて、TPOをわきまえた行動を心掛ける。」そこではどのように行動するべきなのか、考えて行動することができる行田中生であってほしいから。できていないのは一部の人だったと思うのですが、その一部の人に流されて、しっかりできていた人までが「まぁ、いいか」「あ、気づかなかった」そんな感じになってきているように感じるのですが・・・。特に3年生。サイレントゾーンと隣り合わせで学校生活を送っている学級が多くありますが、そのことに悪い意味で慣れてしまっていませんか。特に昼休みと帰りの会が終わった後です。下級生に手本を示すべき3年生がそれでは困ります。1年生、2年生も気が付いた人が気づくことができない人に注意を促す。それが自然にできるきみたちであってほしいと思います。
ものは考えよう
令和7年5月16日
ゴールデンウイークも過ぎ、5月も半ばを迎えました。校外学習、修学旅行の準備も進み、今日は2年生が鎌倉へ校外学習に行っています。新年度が始まって随分時間が経っているように感じますが、ちょっと振り返ってみてください。本年度の始業式が4月7日。入学式が8日。その後18日まで学年日課が続きました。学年日課では身体測定や体力テスト、学級の役割分担を決めるなど、授業はほとんどなかったのではないでしょうか。実際に授業が始まったのは21日からです。1年生の部活動については、本入部の届を出して本格的に活動が始まったのはゴールデンウイーク明けです。
さて、何が言いたいのか・・・まだまだ間に合うということ。勉強、部活動、ここまでなかなか前向きに取り組めていなかった人も、ものは考えようです。授業は始まってまだ1か月も経っていない。1年生の部活動に至っては、まだ1週間しか経っていない。勉強、部活動以外のことも、ここからならまだまだ挽回できると思います。
学校生活に不安に感じているキミ、迷っているキミ、 「よし、ここから気持ちを入れなおすか!」「部活動、入ってみようかな」 まずは自分から動き出してみよう! まだまだ間に合うよ。
感性豊かな・・・
令和7年5月7日
始業式、入学式でもお話ししたとおり、今年度から学校教育目標が変わりました。
「豊かな感性をもち、互いを高め合うことのできる生徒の育成」
学校教育目標とは、私、校長をはじめとして全ての先生方で「このような子供たちを育てていこう」という、言わば先生たちが教育活動を行う上での旗印のようなものです。ですから、行田中学校の生徒である皆さんには「豊かな感性を持った人」に育って欲しいと先生方は願っています。
ところで、この学校教育目標の中にある感性とは・・・「さまざまなものを見たり聞いたりしたときに感じる心の動きや、物事からの刺激から生まれた感情を表現する力。 物事を心に深く感じ取る働き」 きみたちに大切にしてもらいたいこと。それは感性を磨いて欲しいということ。身の回りで起こった事柄や見聞きしたことを他人事としてとらえるのではなく、深い想像力、洞察力を働かせ、自分ごとと置き換えて考えて欲しい 。
ICTなど科学技術の発展に伴い、実体験のない中で知識だけが豊富になっていく、自身の考えのない中で一通りの作品が作り上げられていく。そのような中にあっても、実際に見聞きすることで起こる心の動きや、体験することで得られる刺激を大切にしながら、きみたちには感性を磨いていってもらいたいと願います。
心のこもった・・・
令和7年5月1日
先日、本校を訪れた他校の校長先生が「行田中学校は校舎の外も中もきれいだね」開口一番このようにお話しになりました。本年度は昨年度よりレベルアップを目指して、「心のこもった挨拶・清掃・歌声」を合言葉にしました。その成果が早くもあらわれ始めているのでしょうか。先生や用務員の方々、ボランティアで花の植え替えを行ってくださっている方々の努力も忘れてはいけませんが、きれいな状態を保つためにはやはり何といっても、この行田中学校で過ごしている916人ひとりひとりが、清潔感あふれるきれいな環境を保っていこうという想いをもつことが大切です。明日は授業参観。みなさんのご家族は、行田中学校の生活環境をどのように評価してくださるでしょうか。実は毎回話題になることで、教室内の個人ロッカーや副教材を入れておくケースなどが乱雑であったという感想が・・・・・整理整頓も清掃の中に含まれます。そこには課題としている個々の「心」があらわれます。さて本年度は・・・・・。
気が付いていますか・・・
令和7年4月23日
みなさんに問題です。「サイレントゾーン」とはどのような場所ですか。・・・・・声を出さずに静かに通行したり、過ごしたりする場所のことです。もちろん挨拶の仕方も黙礼です。みなさんもそれぐらいはわかっていますよね。では、行田中学校校舎内にもサイレントゾーンがありますが、どこにあるか気が付いていますか。・・・・・図書室前から職員室へと続く廊下です。もちろんそこにかかる階段も含まれます。続けてもうひとつ、みなさんに問うてみたいと思います。なぜその場所を「サイレントゾーン」としているのでしょうか。・・・・・たとえ休み時間であれ、職員室では先生方が大切な打ち合わせや連絡をしています。事務室、校長室では電話や来客者への応対をしています。そのような時に大きな話し声や笑い声、ドタバタ走ったりする音が聞こえてきたら・・・想像してみてください。
「サイレントゾーン」と表示がなくてもそこがどのような場所であるのか、そこではどのように行動するべきなのかを考えることができる行田中生であってほしいと思います。そういえば最近、校舎内で必要以上の大声や奇声、おおげさな笑い声も聞こえてきたりします。周りで困っている仲間もいるのではないかと思います。新年度が始まって少し落ち着かない自分に気が付いていますか。
『敬愛』・・・自他を大切にする思いやりのある生徒
令和7年4月15日
始業式、入学式から1週間が過ぎようとしています。1年生は中学校への登下校、新しい仲間たちとの学校生活に慣れましたか。2年生は新しいクラスでの生活どうのように感じていますか。3年生は最高学年としての学校生活、役割は果たせていますか。今現在、「なんとなくうまくいっているかも」「楽しい」「調子いい」そう感じている人ばかりなら良いのですが・・・。自分のことで精一杯のこの時期ではあるけれども、少しでいいので自分の身の周りの人にも目を向けてもらえないかな。「登下校や学校生活になかなかなじむことができていない人」「新しいクラスの中でどうしてよいかわからず戸惑っている人」「自分自身変わろうとはしているものの、うまくいかず元に戻ってしまいそうな人」そのような人いませんか。もし、そのような人に気づくことができたら、「おはよう!」「また明日ね!」そんな簡単な一言でいいから声をかけてあげてください。「こっちにこない?」「一緒に行こう!」「一緒にやろう!」その一言で救われる人がきっといると思います。そしてその一言で救われた人は、次はきっと誰かを救う人になってくれるはずです。思いやりの輪を広げてください。
令和7年度 行田中学校新たな歴史と伝統の幕開け
令和7年4月11日
新年度の学校生活が始まりました。今年も「校長室から」を続けます。
さて、皆さんそれぞれに希望を胸に抱いて新年度を迎えたことと思います。是非、その思いを大切に1年間過ごして欲しいと思います。また、具体的な目標を自ら掲げることも大切。何事にも目的意識をもって活動する。自ら意思決定することを心掛けましょう。
ところで・・・始業式や入学式で何度か話をしているので、繰り返しにはなりますが、この令和七年度に行田中学校は創立50周年を迎えます。50年といえば半世紀。半世紀にわたり脈々と築き上げてきた行田中の歴史と伝統を受け継ぐことはもちろん、きみたちにはこの50周年を機に、行田中の新たな歴史と伝統を築き上げていくための「先駆者」としての活躍を期待しています。個人としても集団としても新たなことにどんどんチャレンジして、互いを高め合うことのできる学校にして欲しいと思います。そのためにまず「挨拶・清掃・歌声」これを昨年度よりも更にレベルアップしていこうという話をしましたね。「心のこもった挨拶・心を込めて清掃・心のこもった歌声」うわべだけではなく、意図するところ、意味するところを理解して行動できるようにしよう。新生行田中学校の幕開けです。
終わり良ければ・・・?
令和7年3月21日
令和6年度も学校への登校はあと2日。最後の締めくくりも大切にしたいものです。最後の締めくくりというと「終わり良ければすべて良し」という言葉をよく聞きますが、私としてはあまり使いたくない言葉です。最後の結果ばかりが重要視されているようで、なんとなくしっくりこないのです。大切にしてほしいのはそこに至るまでの過程。失敗も成功も含めて、その過程で自ら動いて経験、体験してきたものが大事なのだと考えています。「最後の締めくくり」と表現するからいけないのかもしれません。あと2日「最後の最後まで気を抜かずに」こう表現した方が良いですね。「初志貫徹」「徹頭徹尾」このような四字熟語を現在の自分にあてはめて、自身の令和6年度を是非振り返ってみてください。
物事の節目
令和7年3月14日
先日の卒業式の式辞の中で話した内容です。2年生は覚えているかな。1年生はリモートで聞きとりづらかったみたいですが・・・。
竹は節があるから大きく育ちます。竹の節目は竹の成長点で、あのようにすくすく伸びていく竹も、これからまだまだ大きく育つために、節目を作る時はゆっくりと時間をかけて作るそうです。人の一生も同じように、物事の節目は自分自身をより良く成長させるための成長点と言うことができます。物事の節目を迎えた時、ただ時に流されて過ごすのではなく、自分自身でより良く変わろうとする勇気を持つこと。自身の将来を見据え、じっくり時間をかけてたくわえをつくること。ものごとの節目節目を大切に。
実は、この話には続きがあります。節目を迎え、勇気をもってより良く変わろうとしている人を認めてあげて欲しい。「今までこうだったのに、ああだったのに・・・」「何を今さら・・・」「調子に乗ってんじゃん・・・」 これまでの言動を取り上げて心無い言葉を投げかけるのではなく、その勇気を認めてあげて欲しい。本人なりに反省した上で変わろうと努力し始めているのです。
これからの日々は、1年生は2年生に、2年生は3年生に進級するための大切な節目となります。より良く変わろうとする勇気を持つ。変わろうとしている人を認めてあげる。そんな一人一人であって欲しいと願います。
2年生、ありがとう。1年生、無駄じゃないんだよ。
令和7年3月7日
卒業式の予行練習がありました。1,2年生の皆さん、今日はどうもありがとう。式に臨む態度、特に歌声が最高でした。先日の三送会よりも更にバージョンアップした歌声で、卒業する3年生も卒業式に向けて、気持ちがますます高揚してきたのではないかと思います。3年生の先生方もすごく感動していましたよ。特に2年生。少ない時間の中、1年生をリードして、よくあそこまで歌い上げられるようになりましたね。本当に手放しで拍手を送りたい! 1年生。予行練習の間、よく我慢できました。中には「当日、式場には入らないのだから、予行も参加しなくったっていいじゃん。」そう思った人もいるかもしれませんが、参加してどうでしたか。あの厳かな雰囲気はなかなか味わえないものだし、3年生一人一人の思いが詰まったあの迫力ある卒業の歌。圧倒されませんでしたか。私もそうですが、1年生の先生方、2年生の先生方それぞれに1年後、2年後、3年生となって卒業式に向かうきみたちの姿も想像しながら、今日の予行練習に参加していたと思います。当日は2年生が在校生代表で式場に入るけど、1年生にはできたら教室で一緒に歌ってほしい。今日のあの雰囲気を味わえたこと、1、2年生にとってとても大きな財産になると思います。
みつけにいこう!
令和7年3月4日
昨日の「三年生を送る会」卒業する3年生に向けて、とてもあたたかな、心のこもった会だったと思います。1、2年生の皆さん、装飾や歌、寸劇、写真やビデオの編集大変でしたね。どうもありがとう。最後の全体合唱、全校生徒それぞれの学年の「ありがとう」の心が一つになって、とても素晴らしい響きでした。3年生にとっては中学校3年間を振り返ることができた、とても素晴らしい時間であったと思います。
さて、せっかく全校生徒で盛り上がった会の最後に、私が話をするのはふさわしくないような気がしたのですが、話をさせていただきました。その中で一つだけ3年生諸君に伝えたかったこと。「卒業までの残り1週間であの日、あの時、言えなかったありがとう、ごめんなさいの気持ちを伝えてみては・・・」そのひとことが言えなくて、今も後悔している、心残りがある、なんとなく気まずくなって・・・というようなことありませんか。今なら伝えられるかも。あの日、あの時に「忘れてきてしまったもの」「落としてきてしまったもの」「失くしてしまったもの」この1週間で見つけにいってみませんか。卒業式にひとりひとりの笑顔が中学校生活で一番輝くよう、残りの1週間、3年生を送る会のように素敵な時間を過ごしてください。
きっと野菜が食べられるようになる
令和7年2月27日
行田中学校の給食はおいしい! 献立の種類も豊富! みなさんそう思いますよね。私もいくつもの学校に勤めてきましたが、献立の種類の豊富さと、それぞれの食材をおいしく食べられるようにするための工夫は、千葉県内だけではなく、全国的にも学校給食がおいしいと評判である船橋市内でもトップクラスだと感じています。特に野菜の和え物やサラダへの工夫が素晴らしい。野菜というとあまり好きではない、日常的に残してしまうという人も少なくないと思います。でも、本校の給食で出る野菜の和え物やサラダ、おいしいからとにかく一口は食べて欲しい。同じ献立名の和え物、サラダであっても、皆さんが食べやすいようにと少しずつ食材を変えてみたり、和える調味料やドレッシングに工夫を加えているのです。栄養士の御子柴先生と調理員さんたちの細かな努力、気が付いていますか。私も実は野菜嫌いで、中学生の頃は家でほとんど野菜は食べませんでした。ところが、あるドレッシングとの出逢いで野菜サラダが食べられるようになったのです。みなさんの中で野菜の和え物やサラダが嫌いな人、和え物やサラダに対する先入観を捨てて給食で出たものを食べてみてください。きっと野菜が食べられるようになります。
威厳
令和7年2月20日
「威厳」という言葉を知っていますか。人が持つ、重厚さや堂々とした態度を表す言葉です。その存在が他者に対して尊敬を引き起こすほどの強さや品格を持っていることを示します。威厳は、経験や知識などによって獲得されます。
昨年末から、1年生は「先輩」と呼ばれる2年生になるための、2年生は行田中の「顔」である最高学年になるための準備をしっかりしていこうという話をしてきました。2年生諸君。この2日間、昼食時、ランチルームの2階に上がってくると、そこに3年生の姿がない状況に「これからは自分たちが最高学年として、この行田中を背負っていかなければいけなくなる」少しはそのような実感がわいてきたでしょうか。1年生諸君。昨日、法典西小の6年生が中学校での学校生活を学ぶため行田中を訪れました。その姿を見て、「いよいよ先輩になるんだ」という自覚は芽生えてきたでしょうか。そして2年生、3年生になるための「威厳」は一人一人身についてきていますか。「重厚さや堂々とした態度」「尊敬を引き起こすほどの強さや品格」これまでの経験、知識の中で獲得できていますか。自身の言動を振り返って考えて欲しい。3年生諸君。公立受検も終わってほっと一息、羽を伸ばしたい気持ちはわかりますが、卒業まで3年生としての「威厳」を1、2年生に示して欲しい。これから行田中を背負っていく後輩のために。
世の中で一番悲しいことは・・・
令和7年2月13日
今日は、多くの人が自身の教訓や自身への戒めとして用いる「心訓」を紹介したいと思います。みなさん知っていますか。これは福沢諭吉の作として知られていますが、実際には作者不詳です。「心訓七則」とも言われています。
一、世の中で一番楽しく立派なことは一生涯を貫く仕事を持つ事です。
一、世の中で一番みじめなことは人間として教養のない事です。
一、世の中で一番さびしいことはする仕事のない事です。
一、世の中で一番みにくいことは他人の生活をうらやむ事です。
一、世の中で一番尊いことは人の為に奉仕し決して恩にきせない事です。
一、世の中で一番美しいことはすべてのものに愛情を持つ事です。
一、世の中で一番悲しいことは嘘をつく事です。
私も折に触れ、自身の言動をこの「心訓」に重ねては反省するばかりです。
耐雪梅花麗
令和7年2月5日
少しずつですが日の出の時刻が早くなってきました。つい先日までは夕方5時には真っ暗になっていたはずなのですが、最近ではまだまだ明るいまま。木の芽も膨らみを増し、どことなく春の訪れを感じられるようになってきた今日この頃。加えて「暦の上では春」とは言うものの、さすがに2月はまだまだ寒いですね。現在、最強の寒波が日本列島に・・・そんなニュースも聞かれます。万物が息を吹き返すように感じる、あの暖かく穏やかな春を迎える前の最後の試練でしょうか。そんな今だからこそ「うん、うん。」とうなずける言葉があります。「雪に耐えて梅花麗し」西郷隆盛の漢詩の一部です。「梅の花は寒い冬を耐え忍ぶからこそひときわ美しい花を咲かせる。人間も同様に、多くの困難を経験し、耐え、乗り越えてこそ大きなことを成し遂げられる。」そのような意味の言葉です。春を目の前にして訪れた厳しい寒さだけではなく、この学年末、人生の階段をまた一歩のぼるにあたり、思うようにいかないことが多くあったり、大きな壁にぶつかったりと、苦しい思いをしている人も少なくないと思います。「雪に耐えて梅花麗し」ここが「がまん」のしどころです。
光陰矢の如し
令和7年1月30日
1月も終わりに近づいています。冬休み明け、あっという間に日が経ってしまいました。2月は28日しかなく、祝日もあり、この調子でいくと「気が付いたら3月」そして「卒業式」・・・・・。みなさんはこのような言い回しを知っていますか。「1月は往ぬる 2月は逃げる 3月は去る」 1月は「行く」とも言います。正月から3月までは行事が多く、あっという間に月日が過ぎ去ってしまうことを1月・2月・3月それぞれの最初の文字をとって調子よく言ったものです。この言い回しのように3年生は「公立高校の学力検査」1,2年生は「期末テスト」が終わると、2月は逃げるように最後の週を迎えてしまいます。意識して1日1日を大切に過ごすよう心掛けないと、その勢いそのままに3月は去って行って、気が付くと4月・・・。ここからは1日1日の積み重ねを大切に。時は過ぎゆくものではなく、積み重ねていくもの。そのような考えで、これからの自分自身にプラスになるような過ごし方をして欲しいと思います。4月までにやるべきこと、克服しなければならない課題がそれぞれにあるはずです。去年と同じ失敗を何度も繰り返したり、同じことで何度も注意を受けている場合ではありません・・・・・。光陰矢の如し。特にこれから3月にかけては努めて時間を大切に。
大丈夫ですか
令和7年1月22日
この「校長室から」を通じて、きみたちに「こういう人になって欲しい」という私の思いをこれまで何回か発信してきました。今回は少し違った方向からお話をしたいと思います。「こういう人にはなって欲しくない」という話です。
よくテレビドラマ(特に時代劇など)を見ていると、「この人が犯人」「この人が何かやりそう」 演じる役者さんの顔つきや表情から予想できてしまうことありますよね。それはその役者さんが、ドラマの中の役になりきって役を演じた結果、そのような顔つき、表情になってしまうのだと思います。同じように、普段のみなさんの表情からも様々なことを感じ取ることができます。やはり、意地悪なことをしていれば、当然、意地悪な顔つきになってくるものです。隠れてこそこそ良くないことをしていれば、どことなく影を感じる、曇った表情になってくるものです。さて、自分の最近の顔つき、表情、どう感じますか。人は知らず知らずのうちに誰かに迷惑をかけたり、他人を傷つけたり困らせたりしてしまっていることがあります。それは都度、周りの人から注意を受けたりする中で反省し、改めていけばよいこと。しかし、「注意を受けても自分本位、自分勝手な言動で周りの人に迷惑をかける」「故意に誰かを困らせる、苦しませる」これは知らず知らずのうちにではなく、わざと誰かに迷惑をかけ、傷つけ、困らせて自身が楽しむための行為です。
わざと誰かに迷惑をかけ、他人を傷つけ、困らせて楽しむ、そのような人間にきみたちにはなって欲しくない。
周りの人から見ればそのようなことをする人の顔つき、表情は・・・・・。
試練の時
令和7年1月15日
3年生にとって、中学校での学習の集大成ともいえる受験(検)の時が目前に迫ってきました。一人一人のこれまでの中学校生活における努力の足跡が試される、評価されるわけです。当然、普段とは違う緊張感、重圧などを感じながらの生活がしばらく続きます。時には自分を見失いそうになることもあると思いますが、平常心を保って生活することが大切です。では、どうすると平常心が保てるのか・・・答えは「凡事徹底」です。自分がすべきこと、当たり前のことを普段どおりに、できれば普段より入念に徹底して行うこと。浮足立って何もかもが手につかず・・・などということにならにように。
この「凡事徹底」という点では、最近3年生を見ていて「挨拶の仕方が変わった」そのような人が多く見られるようになりました。しっかりと目を見てきっぱりとした態度で挨拶ができる。きっと自分が行ってきたことに自信をもっている人、これからが勝負と本気モードに入っている人なのだろうと思います。挨拶一つをとっても心の内はわかるものです。3年生諸君、試練の時を迎えた今こそ、その時どうすることが大切なのか、是非後輩に身をもって示してほしい。「凡事徹底」自分がすべきこと、当たり前のことを怠りなく普段以上に。それが自分自身を落ち着かせることに、本番で存分に実力を発揮するためのモチベーションにもつながるのです。
節目
令和7年1月7日
新しい年を迎えました。昨日集会で、これからの学校生活における各学年の心構え、また巳年にまつわる話から、行田中学校全体としてこのような年にしていこうという話をしました。覚えていますか。一人一人が必ず実行できるよう、努力してください。
ところで・・・みなさんには学校生活の節目節目で、具体的な「目標」を持って過ごすことの大切さを話してきました。ですから私自身も、1月1日の朝に今年の目標を立てました。私の今年の目標は巳年にちなんで「再生」。巳年の「謂れ」については、他の先生方からも聞いていると思います。ヘビが脱皮を繰り返し成長していくことにつながる「謂れ」がほとんどです。「再生」もそのひとつ。「再生」とは「衰えかかっていたものが生き返ること」「再びこの世に生まれること」。私も昨年、還暦(60歳)という人生の節目を迎えました。衰えを感じることも多くなってきたのですが、だからといって自分自身に妥協してばかりでは老いるばかり。自分自身を更に成長させる、新たな自分自身を発見する、そのような1年にしたいので「再生」を目標としました。
「人は節目節目で変わることができる。」以前、みなさんにそのような話をしたことがあると思います。
さて、みなさんはどのような気持ちをもって新年を迎えたでしょうか。「今年は・・・」「今年こそは・・・」 あなたの今年の目標は。新しい年を迎えたこの節目が自分自身を更に成長させる大きなチャンスです。
素晴らしかった合同発表会
令和6年12月17日
12月14日(土)に近隣の小中学校が集まって開催された「合同発表会」に、本校の1組のみなさんも参加してきました。当日は各学校がこれまで練習を積み重ねてきた特色ある演劇や演舞、演奏や合唱の発表があり、どの学校の発表もとても素晴らしいものでした。もちろん本校1組の皆さんの発表(演舞)もとても素晴らしく、全員がそれぞれの役割で持てる力を存分に発揮していました。12日(木曜日)に行ったプレ発表会の時よりも更に堂々と発表することができていました。でも、本校1組のみなさんの何が一番素晴らしかったかというと、他の学校の発表を見ているときの態度です。場を盛り上げる手拍子、他の学校の発表を称賛する拍手、誰からともなく全員がどの学校の児童生徒よりいち早く気づき、そして節度をもって行っている姿に本当に驚きました。「行田中の生徒は素晴らしいですね。」一緒に見ていた他の先生方に言われて、とても誇らしく思いました。演舞での一人一人の姿もさることながら、誰かに言われたわけでもなく、誰かがするのを待ってからするのでもなく、全員が自然とあのような行動をとれることは本当に素晴らしいことです。昨日の2年生の集会で校歌を歌っているとき、目配せしてニヤニヤしながらその場の雰囲気を乱していた人たちには見習ってもらいたいものです。自身がその場でとるべき行動を判断し、「こうするべき」と自身の意志をもって行動できる1組の皆さんは立派です。
本当の自分は?
令和6年12月13日
突然ですが「~をしているときはすごいのに」「~のときはきちんとしているのに」という、誰かに対する評価を口にしたり、聞いたりすることありませんか。例えば「部活動をしているときはいつも真剣ですごいのに」「実行委員で活動しているときは全体の前でしっかり挨拶できるのに」などなど・・・これって誉められているのでしょうか。裏を返せば「普段はやらない、できていない」ということですよね。やれる自分とやらない自分(やれないのではないのです。実際にやれるところを見せているのですから)どちらの自分が本当の自分か。学校外でのクラブチームや習い事、そこで見せている自分と学校内で生活しているときの自分。リーダーとして活動しているときの自分とフォロワーとして協力しなければならない時の自分。自分の得意なこと、好きなことに取り組んでいるときの自分と苦手なことや気の進まないことをしなければならない時の自分。特に部活や習い事の時と普段の学校生活との差、これはよく言われることですよね。どちらの自分が本当の自分か。本当はやれる自分がいるのに普段からやらないようでは、ここ一番で力を発揮したいときに、本当の自分のもつ力を常に発揮することは当然できませんよね。
言葉のもつ力
令和6年12月5日
先日、毎月定例で行う給食についての会議で、調理員さんの会社の代表の方からこのような話がありました。「最近、給食の配膳をしているとき、いただきます と元気な声で挨拶してくれる生徒が多くなった。配膳を手伝ってあげると、ありがとうございます と言ってくれる。とてもうれしい気分になります。」当たり前のことのようだけど、みなさんのために「おいしい給食を」と心を込めて作ってくれている人にとっては、同じ挨拶でも「こんにちは」よりも「いただきます」「ありがとうございます」「ごちそうさまでした」という挨拶は格別なものなのですね。とても幸せな気分になり、益々「おいしいものを」という気持ちになるそうです。その一言が相手を幸せな気分にも、その逆の状況にもしてしまう。それぐらい言葉のもつ力は大きなものなのですね。
見習いたいものです・・・
令和6年11月29日
最近近隣にお住いの方から、行田中学校の生徒に気遣っていただいた、困っているところを助けていただいた、というお礼の電話が何件かありました。そのうちの1件は、行田東小から車で出ようとしたところ門が閉まっていて、車から降りて開けようとしたところ、本校の生徒が通りかかり、わざわざ門の開け閉めをしてくれたというもの。また、このようなものもありました。雨の中お年寄りが動けなくなっていたところ、通りかかった本校の生徒が、その方を介抱し、行きたかったバス停まで送り届けてくれたというもの。とても素晴らしい判断力と行動力だと思います。「こうしてあげた方がよい」と思ってはいるものの、見ず知らずの人とかかわりを持つということは大変勇気のいることで、多くの人は行動に移すことを躊躇してしまいがちです。でもこの人たちにとっては、善意に従って行動することは当たり前のことで、ごく自然に行動しただけなのかもしれません。
皆さんも「これは良くないことだからやめさせた方がいい」「こうしてあげればきっとこの人は助かるだろう」「この場面ではこのような行動をとるべきであろう」頭の中でそのような判断は日常的に行っていると思います。でも、それをいざ行動に移すとなると・・・。私もなかなか行動に移すことのできない一人だと思います。初めの一歩は勇気がいるかもしれませんが、この人たちのように、自然に自分の善意に従って行動できる人になりたいものですね。
行田中学校はどんな学校?
令和6年11月19日
先日の合唱祭は、各クラス一人一人の真剣なまなざしが指揮者に集中していて、歌声だけではなく見た目にも素晴らしさを感じました。実行委員の皆さんも裏方の仕事を自ら探して動いていて、安心して合唱祭の運営を任せることができました。
当日、閉会式で講師の先生方から、合唱への取り組み方をはじめとして様々なアドバイスをいただきましたが、さて、行田中学校、つまりはきみたちについてはどのような印象をもったのか、とても気になるところです。というのも、私もこれまで立場上、様々な学校を訪問する機会があり、行く学校行く学校で、その学校の、その学校に通う生徒の雰囲気の違いを感じてきたからです。その時感じたその学校に対する印象というものは、その後も強く頭に残るものなのです。そのような中で、自分が勤める学校に訪問してきた人たちが、自分の学校にどのような印象を持ってくれたらうれしいか考えたことがあります。
ー 明るく気持ちの良い環境のもと、笑顔があふれる学校 ー
明るく気持ちの良い環境とは、生活環境だけではなく言語環境にも心地よさを感じる。そしてきみたちだけではなく、先生方も笑顔でいられる学校。そんな印象をもってもらえたら・・・・・。そのためにきみたち一人一人に心掛けて欲しいこととは? 答えはきみたち一人一人に考えて欲しい。 行田中学校の印象とは行田中学校に通うきみたちへの印象です。
思いを合唱(うた)に
令和6年11月7日 立冬
朝晩の冷え込みが徐々に増してきました。今日は立冬。暦の上では冬ですが、最近ようやく夏から秋、秋から冬へと季節が動き始めた感じがします。
気候的には肌寒さを感じ始めましたが、学校内は各クラスの合唱祭への取り組みに熱気を感じる今日この頃です。昨年もそうでしたが、毎時間、様々な歌声が聞こえてくるこの時期は、校長室で仕事をしていてとても心地よさを感じます。そのようなことを感じながら、先日、掲示物にいろどりを添えるため、行田公園に落ち葉を拾いに行った時のことです。音楽の授業中に歌っているきみたちの歌声は、校内よりも行田公園内に大きく響き渡っていることを初めて知りました。きっと私と同じように、行田公園を散歩している方の中にも、きみたちの歌声に心地よさを感じている方がいるのではないかと思います。「一音心奏 思いを合唱(うた)に響かせよう」きみたちの様々な思いを寄せた歌声は、聞いている人に心地よい感動を与えています。15日の本番が楽しみです。
ふと気が付けば・・・
令和6年11月1日
11月に入りました。今朝、カレンダーを切り取っていて思ったこと。「今年もあと1枚じゃん!」2か月が1枚にまとめてあるカレンダーだと、今年もあと1枚。みなさん、今年の始めに立てた目標はどの程度達成していますか。改めて具体的な目標をしっかりと見定めて生活しなければいけないな、と自分自身にも言い聞かせたところです。
先週と話はかぶりますが「挨拶・清掃・歌声」も笑顔あふれる学校にするため目標にしていることの一つです。先週「気になっていること」として清掃を話題にしましたが、先日、学校訪問でいらした先生方から「どこに行ってもごみ一つ落ちていない、清潔で整った生活環境ですね」とほめていただきました。きみたちが事前の清掃活動に一生懸命取り組んだことへの評価だと思います。清掃について考えを改めてくれた人が多くいたのですね。
「挨拶・清掃・歌声」 今、学校敷地内だけではなく、行田公園にも各クラスの歌声が響き渡っています。どんどんレベルが上がってきています。挨拶・清掃についてもレベルアップを! まずは挨拶。挨拶については先生方、友達同士だけではなく、保護者の方々を含め学校内に訪れている方々にも明るく元気な挨拶を!
気になっていること
令和6年10月23日
今年度は「挨拶・清掃・歌声」を合言葉に、笑顔あふれる学校にしていこうという話をしたと思います。以前に、挨拶がすごくよくなっているから自信を持って、という話をしました。現在、合唱祭に向けて音楽の時間だけではなく、昼休み、放課後と校内に各クラスの歌声が響き渡っています。そのような中で、合言葉のもう一つ、清掃についてです。最近、会議や行事などで清掃なしの日が多くあります。日直清掃になってしまう日が週の大半を占めてしまうこともあります。ですから清掃活動のある日は、みんながきれいな環境で過ごすためにはとても大切な日なのですが、一人ひとりの清掃に取り組む姿勢はどうでしょうか。集めたごみの取り残しや清掃が終わったばかりなのにごみが落ちている、清掃道具が出しっぱなし・・・そのような状況を目にすることがしばしばあります。環境が人を変える。身の回りのものの乱れは心の乱れ。気になります。
総体駅伝
令和6年10月17日
12日に総合体育大会の最終競技「駅伝の部」がありました。9日には全校で選手の壮行会を行い、学校全体が選手の健闘を期待してエールを送りました。結果は男女とも8位入賞と大健闘でした。選手たちが掲げた目標5位入賞、県大会出場とはなりませんでしたが、大変立派な成績です。改めて選手の皆さん、その選手をサポートしてくれた駅伝メンバーたちの努力に拍手を送ります。
大会当日の様子を見ていてとてもうれしかったことがあります。たくさんの先生方と生徒のみなさんが、運動公園に集結して選手一人ひとりの走りに声援を送ってくれていたこと。学校全体が一体となって、一つの運動競技(部活動)を応援する機会はあまりありません。なぜ駅伝だけ?そう考える人もいるかもしれませんが、この駅伝だけは一つの部活だけでは選手をそろえることがなかなかできないからです。学校内の全ての運動部に所属している人や学校外でのクラブチームで活動している人の協力の中、選手を選考しているのです。言わば、学校の総力をあげて大会に臨んでいるわけです。ですから、少しでも駅伝に興味のある人、走るのが得意な人、走ることに自信を持ちたい人は、遠慮せず活動に参加して欲しいと思います。今後もこの駅伝への取り組みをが、行田中学校の先生方、生徒のみなさんが一体感を感じる活動へとつながってくれることを期待しています。
何気ないひとことだけど・・・
令和6年10月9日
行田中学校の先生方は、個々に気が付いたところをきれいにしてくれたり、全員で協力してペンキ塗りをしてくれたりと、きみたちが学校生活を気持ちよく送ることができるように心配りをしてくれる先生方です。そんな先生方を見習って、私も時々、校内の掃除やペンキ塗りなどをしているのですが、その時にこれまで務めた学校では聞くことのなかったひとことをきみたちからかけられて驚くことがあります。 「ありがとうございます。」 これ、中学生ではなかなか出てこないひとことだと思います。「私たちのためにありがとうございます。」 何気ないひとことだけど、先生方の思いが伝わっているなと感じる瞬間です。行田中は、そんな素敵なことばかけができる生徒がたくさんいる学校です。
地域への貢献
令和6年10月2日
今朝、部活動朝練習の時間に、野球部の生徒が行田公園を含む地域のごみ拾いを行ってくれていました。地域のため、人々のために働く姿は大変尊いものです。きみたちをこれまで見守り、育ててくれたこの地域の方々のため、そしてこれからも生活の拠点となり、きみたちの故郷となっていくであろうこの地域のために自分自身何ができるか。どの地域も高齢化が進む中、地域に住む中学生の力はとても頼りになるところです。地域のためのごみ拾いを「特別なことをしている」のではなく、自分の住む地域なのだから「当然のことをしている」と考えられる心が本当の意味で尊いのかもしれません。きみたちを守り育ててきてくれたこの地域のために、次はきみたちが自分自身にできることを考える番です。
体育祭を終えて・・・
雨のため、二日間にわたる熱戦が繰り広げられた体育祭。二日間をとおしてグランドいっぱいの声援と一人ひとりの真剣なまなざし、はじける笑顔・・・見ている側まで幸せな気分になる、そんな素晴らしい体育祭でした。きみたちの表情もさることながら、きみたちの一挙手一投足に一喜一憂しながら、全力で君たちをサポートしてくれていた先生方の姿も私の目に焼き付いています。来賓でいらしていた方がこんな話をされていました。「行田中学校には先生の手をわずらわせるような生徒はいないのでしょうね。先生方の元気ではつらつとした姿を見ているとそう感じます。生徒も先生方も本当に雰囲気がいい。」私もそう思います。自慢の生徒、先生方です。先生方が頑張れるのは、何事にも一生懸命に取り組んでくれる君たちの存在があるから。期待に応えてくれるきみたちだからこそなのですよ。
自治活動
体育祭などの学校行事は、必ず各クラスの「実行委員」を中心に活動を進めていきます。この「実行委員」は各クラスの話し合いの場で立候補した人、またはこの人なら任せられると推薦された人たちであると思います。特に立候補した人には、今回の体育祭であれば「このような体育祭にしたい」という強い思いがあって立候補したのではないかと思います。 ただ、私が見ていて思うこと・・・実行委員を「先生方のお手伝い」と考えている人も中にはいるのでは? 「精神一到 団結・努力・情熱」この体育祭のスローガンのもと、自分のクラスは、学年は目指した言動がとれているか?先生方から指示される前に実行委員が中心となって判断し、全体に指示を出してほしい。そして3年生の実行委員は最高学年として、学校全体にも目配り、気配りをしてほしい。実行委員諸君、今後の練習、そして本番でのきみたちの活躍に期待します!
ちょっと、いや、かなりいい話・・・
本日(24日)、定期的に行われる行田中学校区近隣6校の情報交換会がありました。中学校は行田中学校1校ですが、小学校は行田西、行田東、法典西、塚田、塚田南の5校が参加します。各学校の校長先生のほかPTAの方にも参加いただき、各学校の近況報告や今後の予定、話題や課題になっている内容などを報告する中で、6校で協力し合い推進できる教育課題などを話し合っています。今年は「挨拶」を一つのテーマとして6校で取り組んでいるのですが、行田東小の校長先生から「中学生ともなるとなかなか挨拶をしてくれないものだが、行田中の生徒は、朝、信号のところに立っていると、今年行田東小を卒業した生徒だけではなく、みんなが本当によく挨拶をしてくれる、素晴らしい」と感心されていました。きみたちだけではなく、私にとってもとてもうれしいひと言でした。小学生にとって身近な先輩であるきみたちがお手本となって、近隣の小学校にも挨拶の輪を広げよう!
輝け!行田中生!
前期期末テストも終わり、各運動部活動は秋の大会(新人戦)が本格的に始まりました。期末テストの問題を真剣に解いているときの表情、部活動の大会でここ一番で見せる表情、物事に真剣に向き合っているときの表情は一人ひとりとても輝いていて素晴らしい。なぜそのような輝きを放つことができるのか。それはその瞬間に、これまで培ってきた自分自身の全てを出し切ろうとするからだと思います。そして、そこに行きつくまでの努力の度合い、思いの強さがその輝きをより強めるのだと思います。最初から手を抜いて、茶化して、いい加減に物事を終わらせて、言い訳ばかり口から出てくるようでは・・・。 どうせやるならとことん、精一杯、一所懸命に! 期待しています。
挨拶 清掃 歌声
夏休み明けの集会で、挨拶の話をしました。担任の先生から話があったと思いますが、自分から挨拶できる人がとても増えてきています。もっと素晴らしいことに、最近の皆さんの様子を見ているとただ挨拶をするだけではなく、相手の目を見てしっかりと挨拶をしてくれる人が多くなったように感じます。また朝、帰りの挨拶や先生方への挨拶だけではなく、給食の配膳時に調理員さんへの元気な挨拶も聞こえてくるようになり、学校全体が明るい雰囲気になってきています。「相手の目を見てしっかりと挨拶をする。」簡単なように思えるけどこれがなかなか・・・・・。自分自身の行いに自信がもてるよう、まずは挨拶からはじめてみよう。
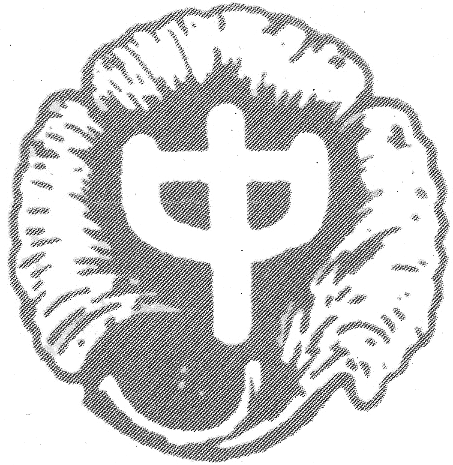 船橋市立
行田中学校
船橋市立
行田中学校
