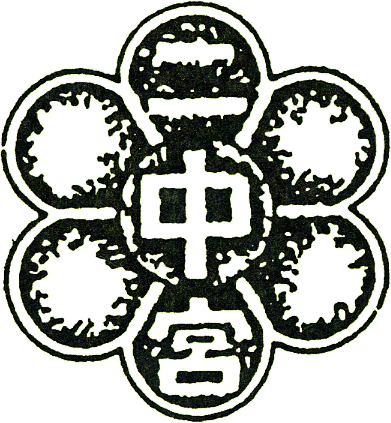 船橋市立
二宮中学校
船橋市立
二宮中学校
- 〒274-0074千葉県船橋市滝台1-2-1
- 047-466-2453
経営方針
|
サブメニュー |
学校紹介 |  沿革 沿革 |
 経営方針 経営方針 |
経営方針『志高く生きる』
今、私達は混迷の時代・激しい変化の時代といわれる見通しのつきにくい中に生きている。
教育界においても同様で、大きな改革の波が押し寄せているところである。特に昨年、一昨年を振り返ってみると、「いじめ」や「体罰」の問題、そして子どもたちの「安全」を守る取り組みは、教育界のみならず社会全体の喫緊の課題となった。
7年前の東日本大震災は、今後の我が国のあり方や仕組みを大きく変える惨事となったことは言うまでもない。「絆や日本人の団結」が叫ばれ、世界に示すことができた反面、復興には、まだまだ長い道のりを要する。文科省のいう「生きる力の育成」はさることながら、「命とは、生きるとは何か?」という根源的な問題を問い直す必要があるのではないかと考える。命のはかなさを思う半面、今生かされている命の大切さを考えずにはいられない。つまり、一人一人が二度とない自分の人生をどう生きていくのかが問われているのである。
古来から洋の東西を問わず「志」の大切さが説かれてきている。例えば、孔子は論語の中で「吾十有五にして学に志す」と説き、吉田松陰は「志を立ててもって万事の源と為す」と説き、ゲーテは「大切なことは大志をいだき、それを成し遂げる技能と忍耐を持つことである」といっている。また、「少年よ大志を抱け」で有名な明治のお雇い外国人クラーク博士は、その後半で「人間が人間として世のため人のためになることを達成するための大志でなければならない」ともいっている。
我々教師は、大いなる志をもって教育にあたるとともに、21世紀の日本を担う生徒には、「志」高く生きてほしいと心から願ってやまない。
以上のような考えにたって、本校の教育目標は、「志高く、知・徳・体の調和のとれた生徒の育成」と設定した。
また、本校の特色ある学校運営のキーワードとして、「継承」「創造」の二点も引き続き掲げた。伝統の中で培われた二宮中学校の教育を「継承」しながらも、新たな取り組みにより、学びの「創造」を図り、生徒一人ひとりの「志」を磨く教育を展開していく。
「志」とは、上記に記した如く、言うなれば「私はこんな人間になりたい。」「そのためにはこんなことに頑張りたい。」と具体的な目標を持たせることである。この「志」は、自分自身のためだけでなく、社会のためになるものであればより高い「志」ということになる。生徒一人ひとりに自分の生き方・在り方をしっかり持たせること、これが人間を成長させる原動力となり、人間性豊かにして、「知」「徳」「体」の調和のとれた人材を育てることにつながると考える。
夢なき者に目標なし 目標なき者に計画なし 計画なき者に行動なし 行動なき者に成果なし
1 教育目標
「志高く、知・徳・体の調和のとれた豊かな人間性と生きる力を身につけた生徒の育成」
2 「めざす生徒像」(学校生活の重点)
|
○志高く生きる生徒(「文武両道」の育成) |
 |
3 「めざす学校像」
・温かい学校(生徒一人一人の良さを認め、より伸ばしていく学校)
・楽しい学校(生徒と教師、生徒同士の信頼しあえる学校、いじめゼロをめざす学校)
・美しい学校(環境美化、整理整頓された学校)
・安全な学校(安全指導・体力作りを推進する学校)
・開かれた学校(地域との相互協力のできる学校)
4 「めざす教師像」
・本校教師であることに誇りを持ち、愛情を持って生徒に接することのできる教師でありたい。
・自分に厳しく、志を高く掲げ、生徒・保護者・地域から信頼される教師でありたい。
(1) 教職に対する強い情熱
・生徒に対する教育的愛情 ・教師としての使命感
・常に学び続ける向上心 ・高い倫理感
(2) 教育の専門家としての力量
・生徒を理解する力 ・生徒指導を実践する力
・学びを支える授業力 ・新たな課題に対応していく力
(3) 総合的な人間力
・心身の健康 ・社会人としての識見と教養
・協働連携していく姿勢 ・人としての信頼される人物
・対人関係能力 ・豊かな人間性
5 育てたい力
(1) 自ら学ぶ(知) 家庭学習の充実と、子どもの表現力を重視した学習態度を育てる。
(2) 自ら育てる(徳) 規範意識を高め、思いやりと感謝の心を育てる。
(3) 自ら鍛える(体) 健康な生活を意識づけ、体力向上に努める。
6 経営の方針
(1) モラールの向上と不祥事根絶(服務規律の厳正)
(2) 安心・安全・防災教育の充実(命を守る教育)
(3) 各指導部と学年の連携を密にした指導体制を確立し、情報の流れをスムーズにし、早い対応ができるようにする。(早期対応・即日対応)
(4) 報告、連絡、相談体制の確立(「悪いことは」は直ちに報告)
(5) それぞれのリーダーを中心として、チームワークのとれた体制を構築する。(人組むは、人の心組む=和を大切に)
(6) H30年度より先行実施、33年度全面実施される新学習指導要領の趣旨を生かした授業づくりを推進するとともに、学力の三要素を意識した授業づくりを目指す。(学力の向上)
学力の3要素
1 基礎的・基本的な知識・技能の習得
2 知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力
3 学習に対する意欲・関心・態度
(7) 常に研究と研鑽を重ね、専門性の向上に努める・特に授業力の向上を目指し、ベテラン・中堅・若手の学び合いを目指す。(専門職としてのプロ意識)
(8) 学校生活・学校行事などを通し、母校に対する誇りを持つ教育の推進(愛校心)
(9) 保護者・地域との積極的な連携を図り、信頼される開かれた学校を目指す。(学校・家庭・地域の連携)
7 経営の重点
(1) 学校経営
・学校教育目標実現に向かって組織で取り組む学校の構築
・全職員協働体制による挨拶・清掃・朝読書・合唱の徹底
・人権意識や規範意識を高め、いじめのない学校をつくる。
・校内の地震防災マニュアルの再チェックと計画的な避難訓練の実施(自らの命を守る態度を養う。)
・「共同実施」の推進・啓発及び事務部内の連携と事務部経営案の検討
(2)学習指導の充実
・授業のねらいを明確にし、指導と評価の一体化を図るとともに、生徒主体で使える学力をつける授業づくり(表現力強化)
・授業規律の構築とわかりやすい授業の工夫(授業のユニバーサルデザイン)
・総合的な学習の計画的な推進と地域の教育力を活用した体験活動等の実践に努める。
・生徒会活動や学校行事・学年行事を活用し、望ましい人間関係、適切な集団行動を体得させる。(生徒会役員のリーダー養成)
・「志を磨く教育」の一貫として「キャリア教育」の推進を図り、将来の夢や目標につなげていく力を育む。
・道徳の教科化に向けた授業を計画的に実践するとともに、全教育活動を通して豊かな人間性を育てる。
・家庭学習の習慣づけ
(3)生徒指導・適応指導の充実
・「自己存在感・自己有用感を与える」「共感的人間関係を育成する」「自己決定の場を与える」を念頭に生徒理解と自立支援に努める。(認めること・評価すること・褒めること)
・挨拶・清掃・読書指導及び合唱指導を全職員一丸となって取り組む。
・部活動を学校の重要な教育活動の一環として捉え、全職員で担当する。
・生徒指導・適応指導にあたっては、速やかな対応を常とする。(その日のうちに対応する)
・「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(H29.2施行)の趣旨を踏まえた不登校生徒に対応を推進する。
・適応指導教室(りんどうルーム)の充実により、不登校生徒を減らす。
・連続3日を超えた欠席生徒の対応は、学年で指導方針を検討する。
・「いじめ防止対策推進法」(H25.9施行)に則り、全校挙げていじめの無い学校作りに取り組む。(早期発見・迅速対応)
(4) 環境・美化
・職員は担当する清掃場所の指導を徹底し、奉仕勤勉の心を育てる。
・教室環境、校内掲示の充実を図る。(ゴミが落ちていない学校・掲示物の破損、はがれのない学校)
・生徒を取り巻く「言語・行動環境の美化」にも注意を払う。(信頼・尊敬される教師を目指す)
(5)保健安全指導の充実
・規則正しい生活習慣、食習慣づくり
・テーマを決め、計画的な「学校保健委員会」の実施
・教職員の勤務実態を把握し、心身共に健康な状態で勤務できる環境をつくる。
(6) 教職員の研修の充実とモラールアップの推進
・校内研修と初若年者研修を通じて授業力の向上を図る。(相互授業参観の実施)
・先進校・研究指定校・近隣小学校へ積極的に出かけ、視察する。
・信頼される教職員として校内外問わず、責任ある言動を心がける。
(7) 信頼される開かれた学校づくり
・学校だより、HP及びメール配信による情報発信と保護者、地域との連携強化
・授業参観・保護者会・面談・PTA活動への参加等で保護者との理解・連携を図る。
・学校評議員会・学校評価を生かした学校経営(学校評価を精査、分析し改善に努める)
・通知表等の保護者への配付物の記載間違いの無いよう、複数の目でチェックする。
(8) 特別支援教育の充実を図る
・通常学級との交流をより充実したものにし、生徒同士が支援し合える関係をつくる。
・インクルージブな教育を視点に、ひとり一人のニーズに対応した支援の充実を図る。
・「障害者差別解消法(H28.4.1施行)」に基づき、障害を理由とする差別の解消を推進し、相互に人格と個性を尊重し合いながら生活する生徒の育成の充実を図る。
