【子ども記者通信】情報活用能力育成研究校の七林中学校(七林中学校 台場 美衣さん)
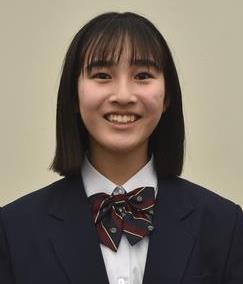
私の通っている七林中学校は、今年度から情報活用能力育成の研究校に指定されています。「情報活用能力」とは世の中の様々な事象を情報とその結びとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりするために必要な資質・能力のことです。
今回は教務主任の有賀先生に、「情報活用能力を育成するために取り組んでいること」そして「情報活用能力はどのような面で役立つのか」についてお話を伺いました。
まず、情報活用能力を育成するための取り組みです。今回は「学習」と「教育」の観点で紹介します。
学習面では、現在1人1台持っているChromebookを使って学習をしています。その例として、デジタルドリルが挙げられます。デジタルドリルでは、5分程度で行える単元ごとにまとめられたドリルで空き時間や授業後に復習として取り組むことができます。それだけでなく、生徒が問題を解けば解くほど苦手分野などからおすすめのドリルを提示してくれるため、効率的に苦手分野の克服に近づくことができます。実際に私もChromebookに入っているデジタルドリルをして、デジタルでの学習は「いつでも・どこでも・誰でも」学ぶことができるのが大きな長所だと感じました。
教育では、「日本教育情報化振興会」が出している「情報活用能力ベーシック」の考えをもとに授業を進めているそうです。情報活用能力において、学習を進める際に大切なステップが(1)課題の設定 (2)情報収集 (3)整理・分析 (4)まとめ・表現 (5)振り返り・改善で、この流れを学ぶことによって情報をうまく使いこなす能力が身につくとおっしゃっていました。先生方は、この流れを1単元あたり5時間ほどで行い、講義をするだけでなく、生徒がそれぞれChromebookを使って情報を調べたり、データを共有したりする授業を行っています。
次に、情報活用能力はどのような面で役に立つのかについてです。この能力は、世の中の出来事を情報と結びつけて捉え、情報や情報技術を適切かつ効果的に活用することで問題を発見・解決したり、自分の考えを形成したりすることに役立つそうです。
今回お話を伺った有賀先生は私の学年の社会の授業を担当してくださっています。授業内では自主的・主体的に授業を進める形を導入していて、「課題設定→情報整理→まとめたものをプレゼンテーションする→振り返る」という流れのもと各自で取り組んでいます。私は今まで情報収集をすることがあまり得意ではありませんでした。しかし、授業を通して、自分で分からないところや追加で調べたいことを膨大なインターネットから正しい情報を見つけることができるようになりました。また、プレゼンテーションの際に作成するスライドも、どのようにしたら人に伝わりやすくなるかを、前回の反省をもとに主体的に考え、工夫することを繰り返したことで、最近は友達から「分かりやすかった」と言ってもらえるようになりました。
将来の予想が困難な社会において、情報を自ら収集し、何が大切かを考え、見いだした情報を活用しながら他者と協働し、新たな価値を創り出すことが重要だそうです。私も「情報活用能力」を身につけ、上手に情報を使えるようにしたいと思います。
(令和7年2月24日投稿)

(中2の春に作成したプレゼンテーション資料 )

(中2の秋に作成したプレゼンテーション資料 )
物事の関係性に注目してまとめられるようになりました。
また、文字数を減らし、大きくしたことでより見やすくなりました!
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 広報課
-
- 電話 047-436-2012
- FAX 047-436-2769
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
- 最近見たページ
-


