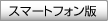発議案(議員提出議案)令和7年第4回定例会
ページID:141971![]() 印刷
印刷
発議案第1号 臨時国会での衆議院議員定数の削減を行わないことを求める意見書
(提出者)岩井友子
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、松崎さち、金沢和子
自由民主党と日本維新の会による高市連立政権が発足したが、連立政権の合意書には「一割を目標に衆議院議員定数を削減するため、令和七年臨時国会において議員立法案を提出し、成立を目指す」ことが盛り込まれた。さらに、日本維新の会の代表は比例代表の50程度の定数削減を主張し、比例定数削減が「一番スピーディーだ」と記者会見で述べている。
しかし、日本の国会議員定数は国際的に見ても少なく、議員1人当たり人口はイギリスの3.8倍、フランスの2.5倍、ドイツの1.5倍など、州政府のあるアメリカを除くと主要7か国では最下位となっており、議員定数削減はさらに民意を届きにくくするものである。
また、比例代表は多様な民意を反映する役割を持っており、比例定数削減は多様化する民意に逆行することとなる。
さらに、現在、定数を含め選挙制度については衆議院選挙制度に関する協議会で、自由民主党や日本維新の会の代表も参加し、与野党で議論しているにもかかわらず、一方的に数の力で定数削減を強行することは、議会制民主主義をも踏みにじるものである。
臨時国会で進められようとしている衆議院議員定数の削減は、議会制民主主義の根幹である国民の民意を切り捨てることであり、認められない。
よって、国会においては、臨時国会での衆議院議員定数の削減を行わないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長
理由
連立合意による衆議院議員定数の削減は、議会制民主主義を踏みにじり、民意を切り捨てることになるため実施すべきではない。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第2号 「スパイ防止法」制定の中止を求める意見書
(提出者)松崎さち
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子
自由民主党と日本維新の会は連立政権合意書に、「インテリジェンス・スパイ防止関連法制(基本法、外国代理人登録法及びロビー活動公開法等)について令和七年に検討を開始し、速やかに法案を策定し成立させる」と明記した。国民民主党や参政党も「スパイ防止法」制定を公約にしている。
1985年に自由民主党が国会に提出した「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」は、国防や外交に関わる秘密の範囲・行為類型が広範囲・無限定で、国会議員の国政調査、報道や言論活動、市民の日常会話まで監視・摘発・処罰の対象とし、最高刑は死刑とするもので、国民の反対世論の高まりの中で廃案となった。日本弁護士連合会も1987年5月30日、「言論・表現の自由を侵害する危険」を指摘し、「スパイ防止法」制定に反対の決議を上げている。
1917年にスパイ防止法ができた米国では、敵国の手先とみなされたら、反戦活動をした人々さえも処罰・弾圧された。冷戦時代は「赤狩り」で大がかりなレッドパージが起き、戦後の日本でも公務員や民間企業労働者が職場から排斥された。「スパイ防止法」は同様の状況をつくりかねない。共産主義者のみならず社会主義者、自由主義者、宗教者などに弾圧を広げた戦前の治安維持法のように、国民監視を強化し、思想までも徹底的に言論弾圧するようなことが起きる危険がある。
そもそも日本には、国家公務員法、地方公務員法、自衛隊法など、広範囲で公務員の秘密漏えいを防ぐ法律があり、さらに特定秘密保護法、能動的サイバー防御法なども制定され、その上に「スパイ防止法」を積み重ねるのは屋上屋と言える。
政府の恣意的な運用により、国民の知る権利をはじめとする基本的人権を侵害し、自由を脅かし、萎縮を招くことで「戦争国家づくり」を本格化させるような法律の制定は、断じて許されない。
よって、政府においては、「スパイ防止法」制定を中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣
理由
国民の言論・表現の自由を侵害する「スパイ防止法」制定の動きが活発化している。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第3号 後期高齢者医療費窓口負担を一律1割に引き下げることを求める意見書
(提出者)神子そよ子
(賛成者)かなみつ理恵、松崎さち、金沢和子、岩井友子
物価高が国民生活を直撃するなか、令和4年(2022年)10月、当時の自公政権は、「現役世代の保険料負担の軽減」などを理由に世代間の対立をあおり、75歳以上の高齢者の医療費窓口負担を引き上げた。原則1割だった窓口負担を、年収200万円以上の単身世帯と年収320万円以上の複数世帯について2割にしたが、その際、3年間に限り、外来受診の月額負担増を3,000円に抑える緩和措置を設けた。
しかし、令和7年(2025年)9月30日をもって、その緩和措置が終了し、10月1日より緩和措置の対象から外され医療費負担が2割になる高齢者は、310万人にも上ると推定される。
平成20年(2008年)に制定された後期高齢者医療制度では、75歳になると会社勤めでも無職でも扶養に入っていても、全て、これまで加入していた医療保険(国民健康保険、被用者保険など)から切り離され、強制的に後期高齢者医療制度へ移行することとなった。
そもそも高齢者は若者より病気になるリスクが高く、日本の高齢者医療費窓口負担は、無料や数百円の定額負担に抑えられていたにもかかわらず、窓口負担が引き上げられ、医療費が生活に重くのしかかっている。
医療費の窓口負担が2割に跳ね上がることにより、受診抑制、治療の中断が重症化を招き、命が奪われることにもなりかねない。
よって、政府においては、75歳以上の高齢者の医療費窓口2割負担を廃止し、一律1割負担に引き下げるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
理由
病気にかかりやすく、治療に時間もかかる所得の少ない高齢者の窓口負担増は、受診抑制により逆に医療費増を生む結果になり、現役世代へも影響することになる。高齢者の命と健康を脅かすだけの制度は廃止すべきである。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第4号 労働時間規制の緩和を行わないよう求める意見書
(提出者)金沢和子
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、松崎さち、岩井友子
令和6年度(2024年度)の「過労死等の労災補償状況」によれば、過重労働や仕事のストレスによる死亡や疾患など「過労死等」の労災認定件数は、前年度より196件増加し、過去最多の1,304件となった。
平成27年(2015年)には、広告大手である電通の女性社員が過労自殺した事件を受け、働く人の健康を守るための法整備が進められたはずである。
しかしながら、平成31年(2019年)に施行された働き方改革関連法では、残業時間の上限を月45時間、年間360時間と定めつつ、労使合意があれば月100時間未満、または複数月平均で月80時間以内、年間720時間まで認められている。これらの上限は「過労死ライン」とされており、依然として過労死の危険が残されたままである。
こうした状況にもかかわらず、高市早苗首相は上野賢一郎厚生労働大臣に対し、時間外労働(残業)の上限規制の緩和を検討するよう指示した。報道によれば、その指示内容は「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」とされている。
働き方改革関連法は現在、施行から5年以上を経て見直しの時期を迎えており、高市首相の指示を受けて時間外労働の規制緩和が進む可能性がある。これは、労働者本人のみならず、過労死や過労自殺で家族を亡くした遺族の願いにも背くものである。
よって、政府においては、「過労死ゼロ」の実現に向けて、労働時間規制の緩和を行わないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
理由
「過労死ゼロ」を実現するために労働時間規制の緩和を行わないことが必要である。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第5号 学習指導要領にある、性教育の内容を狭める「はどめ規定」の撤廃を求める意見書
(提出者)かなみつ理恵
(賛成者)神子そよ子、松崎さち、金沢和子、岩井友子
子どもたちの周りには不適切な性的情報があふれている。それらが子どもたちの目に入らないよう環境を整えることは大人社会の責務である。しかし、それら全てを子どもたちからシャットアウトすることは現状では困難である。その結果、子どもたちの性感染症や予期せぬ妊娠、また性的搾取の被害などが起こっている。
子どもたちを守るには、子どもたち自身に正しい性に関する知識を身につけさせる性教育が必要であるが、現在の学習指導要領では小5の理科に「受精に至る過程は取り扱わない」、中学校の保健体育に「妊娠の経過は取り扱わない」という「はどめ規定」が記載されており、その結果、学校での性教育の内容が狭められてしまい、特に性交や避妊の学習が避けられる要因となっている。
文部科学省は「はどめ規定」は禁止ではなく、必要であれば学習指導要領の内容を超えて授業をしても構わないとの見解を示しているが、実際には「性交については教えてはいけない」と解釈している教員や管理職が少なくないとの報告がある。
前述の不幸な結果から子どもたちを守るには、性教育の実践、具体的には「性的同意」やコンドームなどについての教育こそが今、求められている。
よって、政府においては、学習指導要領から「はどめ規定」を無くすよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣
理由
子どもたちを性的被害から守り、被害者にも加害者にもさせないために実際的な性教育が必要である。これが、この意見書案を提出する理由である。