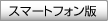発議案(議員提出議案)令和7年第2回定例会
ページID:137969![]() 印刷
印刷
発議案第1号 日本学術会議の独立性・自律性・自主性を脅かす新たな「日本学術会議法」の成立に抗議する決議
(提出者)松崎さち
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子
6月11日の参議院本会議で、現行の日本学術会議(以下「学術会議」という。)を廃止し、国から独立した特殊法人「日本学術会議」を新設する「日本学術会議法」が、可決・成立した。この新法は、憲法第23条「学問の自由」に由来する独立性・自律性・自主性を有しなくなる危険性を内在している。
我が国は、第二次世界大戦を通じて、政治権力による弾圧や動員によって学術研究の自由が奪われた歴史的な経験を持つ。それを踏まえ、学術会議の現行法は、その重要な使命として「科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献…すること(現行法前文)」と規定している。
ところが、新法は、この前文規定を削除し、現行法で明示する職務の独立性を、「運営における自主性及び自律性に常に配慮しなければならない」と変更し、単なる配慮義務に後退させている。
さらに、新法は、中期的な活動計画や年度計画を法定し、学術会議の諸活動に会員以外の者の介入を認める仕組みを幾重にも盛り込んでいる。その仕組みとは、アカデミア全体や産業界等の会員以外の者から会長が任命する科学者を委員とし、会員の選定方針等について意見を述べる選定助言委員会、会員以外の者から会長が委員を任命する運営助言委員会、首相任命の評価委員会や監事、という各機関の設置である。これらの設置は、活動面における政府からの独立性、会員選考における独立性・自律性・自主性というナショナル・アカデミーとしての根幹を損なうものであり、「学問の自由」に対する重大な脅威ともなりかねない。
加えて、政府は、令和2年(2020年)10月に学術会議会員候補者6名を任命拒否した理由をいまだ明らかにしていない。この問題を放置したまま、新法を施行することは看過できない。
よって、本市議会は、学術会議の独立性・自律性・自主性を奪う新たな「日本学術会議法」の成立に抗議する。
以上、決議する。
船橋市議会
理由
学術会議は、戦前・戦中における科学者による戦争協力への反省から、思想・良心の自由、学問の自由、言論の自由を保障するために創立された団体であり、新法はその根幹を損なうおそれが大きい。これが、この決議案を提出する理由である。
発議案第2号 米価高騰を抑え、国産米の安定供給に国が責任を持つことを求める意見書
(提出者)松崎さち
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子
深刻かつ異常な米価高騰が続き、とりわけ低所得者・貧困家庭を直撃している。この理由は、米生産の総量が足りないことにある。
「米不足」が生じた原因は、政府がこれまで「米の消費は毎年減る」として農家に減反・減産を迫ってきたこと、民主党政権が導入した所得補償(10アール当たり15,000円)を平成26年(2014年)に半減し、平成30年(2018年)には全廃し、米農家から1500億円以上もの所得を奪ったこと、米の需給と価格の調整を市場任せにしてきたこと、米の流通の自由化を進め、大手の量販店に価格の決定権を握らせてきたこと、ミニマムアクセス米で輸入を拡大し、生産基盤の弱体化を加速させてきたことにある。
こうした状況下で、近年の米農家は「時給10円」と言われるほど、米を作れば作るほど赤字になる状況に追い込まれてきた。米農家は平成12年(2000年)以降、175万戸から53万戸へと3分の1にまで激減し、生産量も、およそ3割も減っている。後継者が育たず、米を生産する力の減退が深刻である。
ところが、政府はいまだに「米不足」を認めないばかりか、依然として農地の集積・集約を柱に、スマート農業化、輸出拡大を中心的に推し進め、農家に自己責任を迫っている。小規模農家を退場させる政策の下、中山間地では急激に担い手がいなくなっており、農地の荒廃が拡大している。
この危機を打開するには、規模の大小にかかわらず、多様な農業者が希望を持って農業に取り組み、農村で暮らせる条件を政治の責任で保障することが必要である。
よって、政府においては、下記の施策を実施するよう、強く要望する。
記
1. 気候や経済変動などで需給ギャップが生じても米不足とならないよう、米の需給計画は、ゆとりある生産量を確保すること。
2. 備蓄米を「経費節減」として91万トンにまで減らしてきた方針を見直し、買入れ量を計画的に増やし、少なくとも200万トン以上に増やすこと。
3. 米農家への価格保障・所得補償を充実し、大小多様な農業経営を支援すること。農林水産省予算を緊急に1兆円増やし、食糧の安定供給に責任を持つこと。
4. ミニマムアクセス米の主食枠拡大など、米の輸入拡大は行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣
理由
米は日本国民の主食であり、「生産者に再生産可能な価格・所得を保障し、消費者には納得できる手頃な価格で提供する」ことは国の責任である。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第3号 地域医療を守るための財政支援措置及び診療報酬再改定を求める意見書
(提出者)神子そよ子
(賛成者)かなみつ理恵、松崎さち、金沢和子、岩井友子
帝国データバンク動向調査(2024年)によると、令和6年(2024年)の医療機関(病院・診療所・歯科医院)の倒産は64件、休廃業・解散は722件となり、それぞれ過去最悪を更新した。
令和6年度(2024年度)診療報酬改定では、本体改定率が0.88%とされたが、全国の医療機関は公立・民間を問わず、物価高騰や人材流出、消費税負担などにより経営危機に陥っている。
多くの医療機関が「病院が今、危機的状況にあり、地域医療は崩壊寸前である」「病院はどこも明日倒れるかどうかの瀬戸際に立たされている」「このままでは、ある日突然病院がなくなる」との悲痛な声を上げている。
船橋市立医療センターも例外ではなく、地域医療の中核的な役割を担う公立病院として、令和7年(2025年)5月29日には、船橋市長・柏市長が連名で、総務省及び厚生労働省に対し「公立病院の建て替え及び経営に関する要望書」を提出している。その中では、昨今の物価高、人件費の上昇が公立病院の経営を圧迫していることから、病院経営への緊急的財政支援を強く要望している。
医療機関の事業と経営の危機は、国民の医療を受ける権利の危機でもある。
本来、診療報酬は地域のニーズに応え、適切な医療を提供し、健全な経営維持を可能とすべきものである。しかし、令和6年度(2024年度)の診療報酬改定は、医療機関の願いに応えるものとはかけ離れた改定であり、このままでは次期改定までの間に、病院がなくなる地域が出てくることが、現実のものとなろうとしている。
よって、国会及び政府においては、緊急的な財政支援と診療報酬再改定を実施するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
理由
地域医療を守り、国民の医療を受ける権利を守るためには、緊急に財政支援と診療報酬再改定を実施することが必須と考える。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第4号 教育予算の充実に関する意見書
(提出者)文教委員長 松崎さち
教育における諸課題の解決に向け、子供たちの教育環境を整備し、様々な教育施策を展開するためには、十分な教育予算の確保が必要だが、今日の地方自治体の厳しい財政状況を見たとき、国からの財政的な支援等は不可欠である。
よって、政府においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが国民共通の使命であることを再認識し、充実した教育を実現するため、以下の項目を中心に、令和8年度(2026年度)に向けて教育予算の充実を図るよう、強く要望する。
記
1. 災害からの教育復興に関わる予算を拡充すること。
2. 子供たち一人一人にきめ細やかな指導をするため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること。
3. 保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること。
4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助・奨学金事業に関わる予算をさらに拡充すること。
5. 子供たちが安心して学校生活を送れるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の相談体制を充実させること。
6. 多様な学びの場の充実を図り、誰もが学ぶことができる機会を保障するため、必要な予算措置を講じること。
7. 安全・安心で個別最適な学びを実現する施設環境の整備に向け、バリアフリー化や洋式・多目的トイレ、空調設備の設置等、公立学校施設の整備費を充実させること。
8. GIGAスクール構想を着実に推進し、学校現場における様々な課題に対応できる環境を整備すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣
理由
充実した教育を実現するため、令和8年度(2026年度)に向けて教育予算の充実を図る必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第5号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書
(提出者)文教委員長 松崎さち
義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育機会の均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的、地理的条件等にかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定水準の教育を確保するために設けられた制度である。
地方財政においてもその厳しさが増している今日、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
よって、政府においては、義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣
理由
義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持する必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。