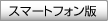(提出者) 議会運営委員長 岡田とおる
船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
|
改正後
|
改正前
|
|
目次
第1章 (略)
第1節~第8節 (略)
第9節 公聴会及び参考人(第78条―第84条)
第10節 (略)
第2章~第9章 (略)
附則
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件を全て議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(会議時間)
第9条 (略)
2 議長は、必要があると認めるときは、会議に宣告することにより、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
4 (略)
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(投票)
第29条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(委員会の審査又は調査期限)
第44条 (略)
2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第38条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、議会において審議することができる。
(発言の許可及び場所)
第50条 発言は、全て議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 (略)
(発言の通告をしない者の発言)
第52条 発言の通告をしない者は、通告した者が全て発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2及び3 (略)
(発言内容の制限)
第55条 発言は、全て簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 (略)
(答弁書の配布)
第66条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写しを議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
(表決問題の宣告)
第67条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(起立による表決)
第70条 議長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第71条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 (略)
(簡易表決)
第76条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第77条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決を採らなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。
第9節 公聴会及び参考人
(発言の許可)
第114条 委員は、全て委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。
(発言内容の制限)
第116条 発言は、全て簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 (略)
(委員外議員の発言)
第117条 (略)
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(発言の取消し又は訂正)
第124条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。
(選挙規定の準用)
第127条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、第1章第4節の規定を準用する。
(表決問題の宣告)
第128条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(挙手による表決)
第131条 委員長が表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 委員長が挙手者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第132条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 (略)
(簡易表決)
第137条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第138条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案が全て否決されたときは、原案について表決を採る。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第144条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求しなければならない。
(資料等の配布許可)
第157条 議場又は委員会の会議室において、資料等を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第159条 全て規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
(懲罰動議の審査)
第161条 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することができない。
(代理弁明)
第161条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わって弁明させることができる。
|
目次
第1章 (略)
第1節~第8節 (略)
第9節 公聴会、参考人(第78条―第84条)
第10節 (略)
第2章~第9章 (略)
附則
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(会議時間)
第9条 (略)
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 (略)
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(投票)
第29条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備付けの投票箱に投入する。
(委員会の審査又は調査期限)
第44条 (略)
2 前項の期限までに審査又は調査を終わらなかったときは、その事件は、第38条(付託事件を議題とする時期)の規定にかかわらず、会議において審議することができる。
(発言の許可及び場所)
第50条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2 (略)
(発言の通告をしない者の発言)
第52条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終わった後でなければ発言を求めることができない。
2及び3 (略)
(発言内容の制限)
第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 (略)
(答弁書の配布)
第66条 市長その他の関係機関が、質疑及び質問に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、議長は、その写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布に代えることができる。
(表決問題の宣告)
第67条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(起立による表決)
第70条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第71条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 (略)
(簡易表決)
第76条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第77条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より先に表決をとらなければならない。
2 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
3 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
第9節 公聴会、参考人
(発言の許可)
第114条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。
(発言内容の制限)
第116条 発言は、すべて簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 (略)
(委員外議員の発言)
第117条 (略)
2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。
(発言の取消し又は訂正)
第124条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。
(選挙規定の準用)
第127条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については第1章・第4節の規定を準用する。
(表決問題の宣告)
第128条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(挙手による表決)
第131条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 委員長が挙手者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第132条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 (略)
(簡易表決)
第137条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第138条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第144条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第157条 議場又は委員会の会議室において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、議長又は委員長の許可を得なければならない。
(議長の秩序保持権)
第159条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。
(懲罰動議の審査)
第161条 懲罰については、議会は、第37条(議案等の説明、質疑及び委員会付託)第3項の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して議決することはできない。
|
|
|
|
|
|
附則
この規則は、公布の日から施行する。
理由
標準市議会会議規則の一部改正にならい、会議時間を変更する場合の手続等について、所要の改正等を行う必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。
(提出者)神田廣栄
(賛成者)松嵜裕次、浅野賢也、鈴木和美、岩井友子、齊藤和夫、日色健人
船橋市議会個人情報保護条例(令和5年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
|
改正後
|
改正前
|
|
(定義)
第2条 (略)
2~9 (略)
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。第12条第5項において「番号利用法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
11~13 (略)
(利用及び提供の制限)
第12条 (略)
2~4 (略)
5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号までの規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
| (略) |
(略) |
(略) |
| 第38条第1項第1号 |
又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき |
第12条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第10項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき |
| (略) |
(略) |
(略) |
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1)~(9) (略)
2 (各号列記以外の部分略)
(1) (略)
ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与若しくは報酬若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの
イ~カ (略)
(2)及び(3) (略)
3 (略)
(開示請求権)
第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第27条 (略)
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)及び(2) (略)
3 (略)
(訂正請求権)
第31条 (略)
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 (略)
(訂正請求の手続)
第32条 (略)
2 (略)
3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(利用停止請求権)
第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)及び(2) (略)
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 (略)
(利用停止請求の手続)
第39条 (略)
2 (略)
3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第53条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
|
(定義)
第2条 (略)
2~9 (略)
10 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
11~13 (略)
(利用及び提供の制限)
第12条 (略)
2~4 (略)
5 保有特定個人情報に関しては、第2項第2号から第4号まで及び第29条の規定は適用しないものとし、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
| (略) |
(略) |
(略) |
第38
条第1項第1号 |
又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき |
第12条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき |
| (略) |
(略) |
(略) |
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第17条 議長は、その定めるところにより、議会が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項その他議長が定める事項を記載した帳簿(以下「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
(1)~(9) (略)
2 (各号列記以外の部分略)
(1) (略)
ア 議会の議員若しくは議員であった者又は職員若しくは職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準ずる事項を記録するもの
イ~カ (略)
(2)及び(3) (略)
3 (略)
(開示請求権)
第18条 何人も、この条例の定めるところにより、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下この章及び第48条において「開示請求」という。)をすることができる。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第27条 (略)
2 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第24条第1項の決定(以下この章において「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、議長が定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他議長が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1)及び(2) (略)
3 (略)
(訂正請求権)
第31条 (略)
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この章及び第48条において「訂正請求」という。)をすることができる。
3 (略)
(訂正請求の手続)
第32条 (略)
2 (略)
3 議長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この章において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(利用停止請求権)
第38条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、議長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この章において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(1)及び(2) (略)
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この章及び第48条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 (略)
(利用停止請求の手続)
第39条 (略)
2 (略)
3 議長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この章において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第48条 議長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、保有個人情報の特定その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
第53条 職員若しくは職員であった者、第9条第2項若しくは第15条第5項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は議会において個人情報、仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第54条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第55条 職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
|
|
|
|
|
|
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から施行する。
⑴ 第2条第10項の改正規定(「以下」を「第12条第5項において」に改める部分に限る。)、第12条第5項の改正規定(「及び第29条」を削る部分に限る。)並びに第17条第1項各号列記以外の部分及び第2項第1号ア、第18条第1項及び第2項、第27条第2項、第31条第2項、第32条第3項、第38条第1項及び第2項、第39条第3項並びに第48条の改正規定 公布の日
⑵ 第2条第10項の改正規定(「第2条第8項」を「第2条第9項」に改める部分に限る。)及び第12条第5項の改正規定(「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める部分に限る。) 令和7年4月1日
⑶ 第53条、第54条及び第55条の改正規定 令和7年6月1日
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
理由
刑法の一部改正等に伴い、規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
(提出者)かなみつ理恵
(賛成者)神子そよ子、松崎さち、金沢和子、岩井友子
一昨年12月に沖縄本島中部で米軍嘉手納基地所属の米空軍兵が16歳未満の少女を車で連れ去り、性的暴行を加えた事件があった。その後、この米空軍兵はわいせつ目的の誘拐と不同意性交の罪に問われ、昨年12月13日の那覇地裁での判決公判で懲役5年の実刑判決が言い渡された。
この事件を知った人の多くは、平成28年(2016年)4月に沖縄県うるま市で元海兵隊員が20歳の女性を暴行し殺害した犯罪を、そして平成7年(1995年)に沖縄本島北部で海兵隊員ら3人による女子小学生への暴行事件を想起した。そして「またもや」や「何度繰り返せば」といった怒りと嘆きの声が沖縄はもとより日本中から多く上がった。
再発防止策として、米軍は隊員の教育やリバティー制度(行動規制)の見直しなどを実施しているが、昨年11月には海兵隊員による20代女性への不同意性交等致傷事件が発生した。この事件は嫌疑不十分で不起訴処分になりはしたが、沖縄では同様の事件が一昨年の事件以降に、この件以外でも4件も発生している。さらに上記制度の見直し後の昨年10月以降でも刑法犯が11件、交通人身事故2件など、計26件も発生している。これらの事実をもってしても、米軍の再発防止策が実効性に乏しいことは明らかである。
また、これらは沖縄だけの問題ではない。米軍岩国基地のある山口県や隣接する広島県、三沢基地のある青森県、佐世保基地のある長崎県、横須賀基地のある神奈川県、横田基地のある東京都でも窃盗や性的暴行を米軍関係者は引き起こしている。
平成8年(1996年)から令和5年(2023年)までの27年間で米軍人・軍属による刑法犯検挙件数は2,132件もある。これらの米軍人等による犯罪が相次ぐ要因は、米軍に治外法権的な特権を与えている日米地位協定によるところが大である。
船橋市には米軍基地はないが、自衛隊の習志野駐屯地には平成29年(2017年)以降、米軍が複数日滞在するようになっており、その間の米兵らの飲酒や駐屯地からの外出が許されている現状を鑑みれば、今後、沖縄や他の米軍基地周辺と同様の米軍関係者による犯罪が起こる懸念が拭えない。
よって、政府においては、下記の事項を実施するよう、強く要望する。
記
1. 米軍構成員等を特権的に扱う日米地位協定の抜本改定を行うこと。特に、身柄引き渡し条項を早急に改定すること。
2. 日本政府の責任の下で実効性のある米軍人等による犯罪防止策を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣
理由
米軍関係者によるこれ以上の犠牲者を出さないようにする必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。
発議案第4号 訪問介護事業者への介護報酬引き下げ撤回などを求める意見書
(提出者)岩井友子
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、松崎さち、金沢和子
2月17日に発議案第4号の提出者(岩井友子議員)から次のとおり訂正申出があり、2月28日の本会議において承認されました。
──────────────────────────────────────────────
令和7年2月13日に提出した発議案第4号「訪問介護事業者への介護報酬引き下げ撤回などを求める意見書」の一部に誤りがあり、下記のとおり訂正したいので、会議規則第19条第2項の規定により請求します。
記
訂正の内容
令和7年第1回船橋市議会定例会発議案22ページの記の4中「国庫負担」を「公費負担」に訂正する。
理由
錯誤のため
令和6年(2024年)4月からの介護報酬改定では、介護サービス全体は1.59%の微増だったが、訪問介護の基本報酬が2%~3%引き下げとなった。
この介護報酬の引き下げは訪問介護事業所を運営する事業者にとって「まさかの引き下げ」となった。経営が苦しい介護業界の中でも、特に訪問介護の経営が苦しいというのが現場の実感である。
平成12年(2000年)の介護保険制度開始以来、物価や最低賃金の上昇にもかかわらず訪問介護の報酬は引き下げられ、令和5年(2023年)には1年間に過去最悪の427社の訪問介護事業者が倒産や休廃業・解散により消えている。事業者がなくなればさらに多くの事業所がなくなり、訪問介護を受けられなくなった多くの利用者が事業所の変更や転居を迫られている。
こうした危機的状況にかかわらず、報酬引き下げを強行したことにより訪問介護事業者の倒産、休廃業等がさらに加速している。その結果、訪問介護事業所が存在しない“空白地域”が全国に広がり、令和7年(2025年)1月8日現在、事業所ゼロの自治体は107町村、事業所が残り1という自治体が272市町村となり、増え続けている。訪問介護の報酬を引き下げた政府の責任は重大である。
次期改定までこの状態が続けば、訪問介護事業所は急速に数を減らし、居住する地域によって基本的な在宅介護サービスである訪問介護を受けられない事態になるのは明らかである。
よって、政府においては、危機的状況にある訪問介護事業を守り、利用者の生活を守るために緊急に下記の事項を実施するよう、強く要望する。
記
1. 次期改定を待たず訪問介護の基本報酬減額を撤回すること。
2. 介護人材の不足を解消するために新たに国費による公的助成の仕組みをつくり、国の責任で介護職員の賃金を「全産業平均並み」に引き上げること。
3. 介護事業が消滅の危機にある自治体に対し、国費で財政支援する仕組みを緊急に創設すること。
4. 給付や報酬が増えると保険料負担が増える矛盾を解決するために、国庫負担50%を60%に引き上げること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣
理由
苦境に立たされている訪問介護事業者の救済など、介護保険事業の安定的な運営を図る必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。
(提出者)神子そよ子
(賛成者)かなみつ理恵、松崎さち、金沢和子、岩井友子
高額療養費制度とは、医療費の家計負担が重くならないよう、大きな病気や事故で高額な医療費がかかった際、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費について、年収に応じて月ごとに上限額を設け、それを超えた額が支給されるという制度である。
がんなどで長期にわたり治療を受け、高額な医療費を負う患者や家族、全世代にとって、欠かせないセーフティーネットであり、まさに「命綱」である。
ところが、政府は令和7年度(2025年度)予算案に、令和7年(2025年)8月から令和9年度(2027年度)にかけて段階的に、低所得者も含め全ての所得層で自己負担上限の引き上げを盛り込んだ。
これに対し、全国がん患者団体連合会は「現役世代の中には、仕事や日常生活を続けながら、ぎりぎりの範囲で医療費を支払い続けている患者とその家族もいる。負担上限を引き上げれば、生活が成り立たなくなる。あるいは治療の継続を断念しなければならなくなる」と危惧を訴えている。
この改悪で国の財政負担は、最終的に1100億円削減される見込みである。政府は、現役世代の保険料軽減を口実にするが、加入者1人当たりの保険料軽減額は、引き上げの最終段階でも月417円、労使折半後はその半額の僅か208円にとどまる。
がんや交通事故のリスクはどの世代にもあり、制度の改悪は国民に自己責任を押しつけ、全世代の不安を増長し、「命綱」を断ち切るものである。
保険料軽減に必要なのは、患者負担引き上げではなく、医療費への国の負担率引き上げである。
よって、国会及び政府においては、高額療養費制度について負担限度額の引き上げを中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣
理由
高額療養費制度はがんや交通事故などで高額な治療を受け、家計に大きな負担がかかる患者やその家族にとっての「命綱」とも言える制度であり、もしもの時にも、全ての国民が安心して治療を続けるための大切な制度である。ここに手をつけ医療費抑制を図るような制度改悪は実施すべきではない。これが、この意見書案を提出する理由である。
(提出者)松崎さち
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子
日本を含めた世界各地で猛暑や豪雨、山火事など、気候変動による激甚災害が顕在化し、温室効果ガスの排出削減が急務となっている。国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の報告では、産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑えるためには、世界全体の排出量を2035年までに2019年比で60%削減する必要があるとしている。
しかし、政府が2035年度目標として示した「2013年度比で60%削減」という数字は、「2019年度比で53%削減」にすぎない。日本は、中国、アメリカ、インド、ロシアに次ぐ排出大国であり、その責任にふさわしい野心的な目標とすることが求められる。
世界では再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)が最も安い電源となり、燃料高の中、エネルギー安全保障上からも加速度的に導入が進んでいる。石炭産出国のオーストラリアやインドネシアも、発電部門で最大の二酸化炭素排出源である石炭火力発電の廃止を決め、再エネの大量導入に動いている。
化石燃料を輸入に頼っている日本でも、再エネ推進の経済効果は大きく、太陽光発電の屋根置きや遊休農地の一部活用だけでも大規模導入が可能だと指摘されている。「日本気候リーダーズ・パートナーシップ」は、1月22日に発した声明で、「脱炭素化の加速・再エネ調達拡大が、企業の死活問題」「2035年75%以上の削減が必要」と指摘した。
欧州などでは大電力の火力発電から、地域住民主体の再エネへ「システムチェンジ」が進められ、地域の活性化につながっている。これらを踏まえて日本政府は、原発回帰、石炭火力の温存などを掲げた方針を見直し、市民社会の声に耳を傾けながら、従来の路線を抜本的に転換すべきである。
よって、政府においては、科学的知見と国際合意を踏まえ、温室効果ガスについて2035年度までに2013年度比で75%~80%の排出削減(2019年度比で71%~77%の排出削減)目標を掲げるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣、環境大臣
理由
日本は、中国、アメリカ、インド、ロシアに次ぐ温室効果ガス排出大国であり、排出削減についても、その責任にふさわしい野心的な目標を持つことが求められる。これが、この意見書案を提出する理由である。
(提出者)松崎さち
(賛成者)かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子
東京大学は昨年9月24日、現行年額535,800円である学士課程の授業料を、今年4月入学者から年額642,960円に値上げすると発表した。修士・専門職学位課程(法科大学院を除く)も、令和11年(2029年)4月入学者より同様に値上げとなる。
国立大学では平成31年(2019年)以降、東京工業大学、一橋大学、千葉大学など7大学で学費が値上げされており、東京大学が値上げすることで、国立大学での値上げ連鎖が起きかねない状況である。私立大学でもこの間、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、立命館大学、同志社大学などで値上げが相次ぎ、新たに中央大学や関西大学も来年度からの値上げを発表している。
今でも高い学費、重い教育費の負担に、多くの学生や国民が苦しんでいる。それにもかかわらず、学費値上げが相次ぐ要因は、OECD(経済協力開発機構)の中でも最低水準という状態が長期にわたって続いている、日本の乏しい高等教育予算である。
しかも政府は、平成16年(2004年)の国立大学の法人化後、国立大学全体の基盤的経費である運営費交付金を約1600億円も削減した。その額は中堅・地方大学20大学分への配分額にも相当する。さらに私立大学への私学助成金は、経常費の僅か1割以下に抑制されたままである。そのため、大学は物価高騰を含めた教育コストの増額などから財政難に陥っている。
日本国憲法は教育の機会均等を定めており、その保障は政治の責任である。教育の成果は個人のみならず社会全体のものであり、お金の心配なく誰もが大学で学べるようにすることは、日本の学術振興、科学技術の発展、社会の進歩に大きく寄与する。高等教育の無償化が強く求められる中、少なくとも直面する来年度の授業料値上げを止めることは最低限必要な課題であり、緊急の予算措置を取るべきである。
全国立大学に100億円程度、全ての私立大学、公立大学、専門学校に860億円程度の助成を行えば、来年度の値上げは回避できる。
よって、国会及び政府においては、来年度の学費値上げを止めるため、国公私立大学と専門学校に対し、1000億円規模の緊急助成を行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣
理由
東京大学の学費値上げ発表後、全国の大学で同様に値上げが波及する危険が生まれており、教育の機会均等を一層妨げかねない。これが、この意見書案を提出する理由である。
(提出者)今仲きいこ
(賛成者)神田廣栄、斉藤誠、岩井友子、はまの太郎
核兵器禁止条約は、平成29年(2017年)7月7日に国連で採択されて以来、令和6年(2024年)9月25日時点で、署名国は94か国、批准国は73か国となっている。
令和3年(2021年)1月22日に核兵器禁止条約が発効されたことにより、昭和21年(1946年)に国連総会第1号決議にて原子兵器の撤廃が提起されて以来、人類は初めて核兵器を違法とする国際法を手にした。この条約は、核兵器の開発、実験、生産、製造、使用、威嚇など、核兵器のあらゆる活動を禁止しており、さらに、核兵器の使用を前提とする核の傘も禁じている。
核兵器禁止条約は、国連、非核国政府、被爆者をはじめ非核平和を求める市民社会が力を合わせ実現した素晴らしい条約である。しかし、日本政府は、6年連続で核兵器禁止条約促進の国連決議に反対票を投じるなど、条約に背を向けている。仮に、日本政府が条約に参加すれば、平和を求める国際社会の期待に応え、高い信頼を得て、核兵器廃絶の流れに勢いを与えることができる。
令和6年(2024年)、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞し、核兵器のない世界を願う全ての人々に励ましと勇気を与えている。アメリカの原爆投下によるこの世の地獄をかろうじて生き延びた被爆者たちは、人類の危機を救おうと立ち上がり、核廃絶を願い、自らの苦しい体験を語り続けてきた。
アントニオ・グテーレス国連事務総長は、被爆者のたゆまぬ努力と強靭さは、世界の核軍縮運動の背骨となってきたとたたえた。また、ノルウェー・ノーベル委員会のヨルゲン・フリドネス委員長は、授与発表の会見において、核使用を許さない「核のタブー」を強調した。
唯一の戦争被爆国である日本は、一刻も早く条約に参加し、核兵器のない世界をつくる努力の先頭に立つべきである。また、世論調査においても、7割の国民が、日本は核兵器禁止条約に参加すべきとある。
よって、政府においては、直ちに核兵器禁止条約に署名・批准をするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣
理由
核兵器禁止条約は、国連、非核国政府、被爆者をはじめ非核平和を求める市民社会が力を合わせ実現したものであるが、日本政府は、核兵器禁止条約促進の国連決議に反対をしている。唯一の被爆国として、核兵器全面禁止・廃絶責務を果たす必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。
(提出者)かいさち
(賛成者)神田廣栄、斉藤誠、岩井友子、はまの太郎
日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用等による不利益、不都合を強いられる人が多く存在している。夫婦同姓を法律で定めているのは、日本のみである。婚姻の際、96%が夫の姓になっており、女性に多大な負担となっている。
通称使用では、旧姓併記や旧姓使用の法的根拠がないために、本人であることを疑われたり、様々な事務手続の煩雑さがある。働く女性たちにとっては、改姓によってキャリアが中断されるとの声も切実で、通称使用の拡大では根本的解決にならない。
国連の女性差別撤廃委員会は、夫婦同姓を義務づける民法第750条は差別的規定に当たるとして、平成15年(2003年)以降、繰り返しその改正を勧告してきた。令和6年(2024年)10月には、「第750条を改正する措置が何も取られていない」と厳しい表現で勧告し、再び、2年以内に実施状況の報告を求めている。
平成8年(1996年)、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申したが、既に四半世紀以上が経過している。
平成27年(2015年)及び令和3年(2021年)、最高裁判所は夫婦同姓の強制は違憲ではないと判断しつつも、制度の在り方は国会の議論に委ねるべきとしており、複数の反対意見も付されている。
選択的夫婦別姓制度は、同姓か別姓かを選択できるようにするもので、誰も強制されることのない仕組みである。
最近の世論調査では約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成し、特に、若年層ほど賛成割合が高くなっている。
よって、政府においては、選択的夫婦別姓制度導入に係る国会審議を進めるため、民法その他の法令改正案を国会に提出するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画 共生・共助)
理由
日本では、婚姻における夫婦別姓が認められないために、望まない改姓、事実婚、通称使用等による不利益や不都合を強いられている人が多く存在しており、夫婦同姓を法律で定めているのは日本のみである。選択的夫婦別姓制度を導入することで、誰も強制されることのない仕組みが必要である。これが、この意見書案を提出する理由である。
![]() 印刷
印刷