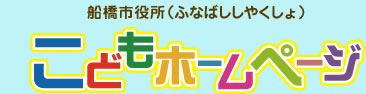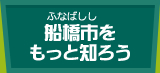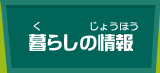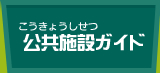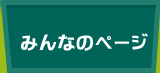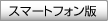こどもホームページ > 市役所の仕事 > まちづくりに関するいろいろな仕事 > 川づくりの仕事

川づくりの仕事
川づくりの目的は、第一にみなさんを洪水から守り、安心して暮らせるようにすることです。第二に、川に住む生き物を育てたり、普段の日は、みなさんが散歩をしたりできるような、自然にやさしい川にすることです。

【工事が完了した二重川】
水循環って何?
地球の水は、海や陸から蒸発して雲となり、雨や雪となって、また陸や海に戻ってきます。陸に戻った水は、川に流れこんだり、地下水になったりします。川の水は、ふたたび海に流れこみます。これを水循環といいます。
現在市内では、林や田畑が減って、家や道路などが増えたので、地下水が溜まらずに直接川に水が流れてきて、それが川の洪水の原因になっています。
そのようなことにならないように、自然に近い状態で雨水などを地下に戻し、以前の水循環のかたちを取り戻そうとすることを水循環系再生といい、現在さまざまな対策を行っています。
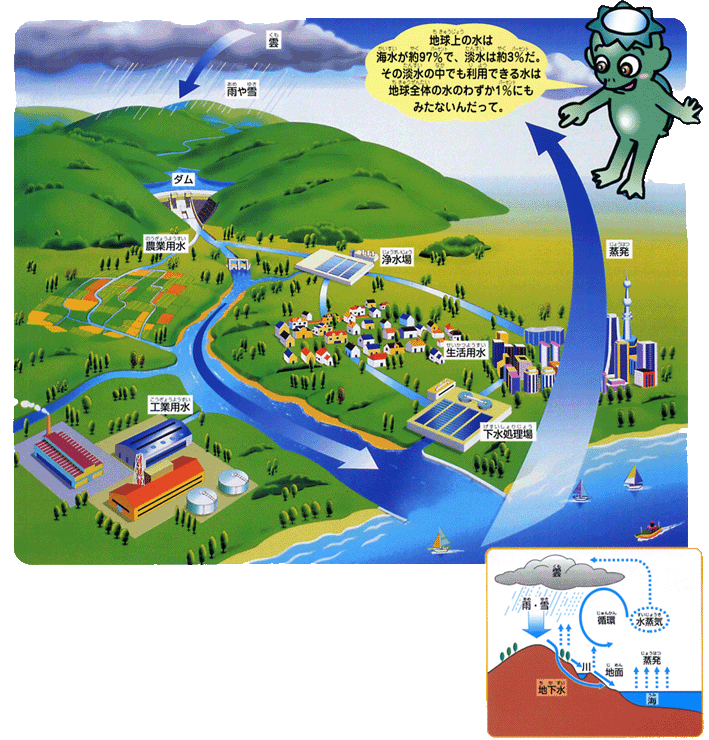
【水循環のイメージ図】
平成12年千葉県河川協会発行「おもしろ川ランド2」より転載
海老川ってどんな川?
海老川の概要
海老川は市内中心部を流れる二級河川であり、八栄橋から海まで2,670mの長さがあります。流域の広さは約27.1km2であり、市内で一番大きな流域面積を持っています。その海老川流域は、田畑に変わってどんどん人が住むようになり、今では世帯数約11万世帯、人口にして約25万人もの人が住んでいます。(令和2年時点)
海老川は、たくさんの支川と呼ばれる川が流れ込んでいて、主なものとして、前原川、飯山満川、念田川、長津川などがあげられます。水源としては、北谷津川の御滝不動尊や前原川の倶梨伽羅不動尊の池、および金杉川の上流部などがあげられます。

【海老川の様子】
海老川の名前の由来
海老川の名前の由来はいろいろ言い伝えられていますが、主なものとして次の5つの説があります。
- エビ(テナガエビ)が多く生息していた川だから。
- エビの形のように曲がった川だから。
- 堰(注)や樋(注)のある川の意味の「イビ川」が変化して「エビ川」になったから。
- 昔、源頼朝が船橋の地を通ったとき、村人が川からとれるエビを差し出したことから。
- 4で差し出した人が「ゑび川三郎左衛門」と言う名前であったから。
以上5つが主な由来として伝えられていますが、1のテナガエビが多く生息していたからというのが有力な説のようです。
(注)堰:川の水をせき止めるために、川や水路中に造ったしきり
(注)樋:川の堤防を横断している管
お問い合わせ先
下水道河川整備課 整備第一係 / 電話番号:047-436-2652 /FAX:047-436-2649/ メールフォーム
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間 : 午前9時から午後5時 / 休業日 : 土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日