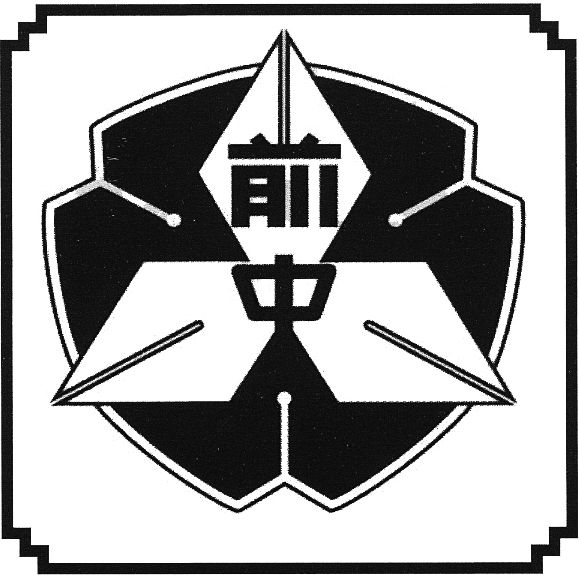 船橋市立
前原中学校
船橋市立
前原中学校
- 〒274-0826千葉県船橋市中野木2-33-1
- 047-478-6831
学級経営の基本的姿勢
1.はじめに
(1) 教育課程の共通理解
まずは、法令(憲法、教育基本法、学校教育法など)や学習指導要領及び県や市の教育施策と重点を基盤として、地域や学校の実態の上に立ち、教育課程の主旨に則り、日々の教育活動の充実を図る必要があります。
特に、教育課程の改訂は、戦後、7回目になり、5年を経過した。特徴として「教育改革」を唱え、広く国民に意識づけをしたことにある。
内容としては「ゆとり」の中で学校は「特色ある教育」を展開し、子どもたちに「生きる力」を育む。すなわち、豊かな人間性や基礎・基本を重視し、個性を生かし、自ら考え、課題を見つけ、課題を解決する能力を育成することにある。それと同時に「確かな学力の向上」をめざすとともに「豊かな心」の育成がアピールされている。
「確かな学力の向上」のアピールの背景には、国民が「ゆとり教育」に対して危機感(学力の低下)を抱いたことに要因があります。「ゆとり教育」は子ども側に立ってのことであり、教職員にとっては「ゆとり」はなく、中長期的な展望を見据えて、計画的に進められる必要があります。決して「緩み」と受け止められてはいけない状況下であり、教育公務員としての使命と考える必要がある。
特に、中央教育審議会答申(平成17年10月26日)「新しい時代の義務教育を創造する」においては、「新しい義務教育の姿」として
『子どもたちが、よく学びよく遊び心身ともに健やかに育つことにある。そのために、質の高い教師が教える学校、生き生きと活気あふれる学校を実現したい。
学校の教育力、すなわち、「学校力」を強化し、「教師力」を強化し、それを通じて、子どもたちの「人間力」を豊かに育てることが改革の目標である。』と述べていることに注視する必要がある。
(2) 教職員の毅然とした姿勢の確立・・・「不易」と「流行」
「教育においては、どんなに社会が変化しようとも、時代を越えて変わらない価値あるもの」(不易)として、考えられる具体的な内容として
- 豊かな人間性
- 正義感や公正さを重んじる心
- 自ら律しつつ、他人と協調し、他人を思いやる心
- 人権を尊重する心
- 自然を愛する心
等をあげることができます。
これらのことを子どもたちに培うことは、いつの時代でも大切にしたいものと考える。他方、「教育は、社会の変化に無関心であってはならない。時代の変化とともに変えていく必要があるもの」(流行)に柔軟に対応していくことも、教育の課題と言われている。しかし、安易に流行に流されてしまうことは、子どもたちに迎合することに繋がります。そのためにも、私たちの共通理解は大切にしたいものです。
2.経営の重点
(1) 授業の質的向上と充実に努める
基礎的・基本的な学習の徹底
- 「わかる授業」の工夫改善と展開に努める。
- 生徒個々の統計や分析を的確に行なう。
- チャイムが鳴ったら授業を開始する。
- 人の話を聞く姿勢を育てる。
- 積極的に発言させる。
学習の個別化と個性化を図る学習方法の改善
個別化・個性化 ・わがまま・放任は違う。あせらず、誉める・叱るの繰り返しを一貫して実践する。
- 場に応じて、一斉学習やグループ学習・個別学習の導入
(2) 基本的な生活習慣の育成に努める
基本的生活習慣の定着化
日頃からの生活習慣が自然に表現されるよう、時間や約束を守り、さらには礼節等の基礎基本の躾の指導をお願いしたい。
キャリア教育の推進
知性や理論のみに終わらせることなく、体験活動や奉仕活動の実践を通して感性を育てたい。それが、強いては「自ら育つ」(自立)方向に導けることに期待したい。
そのためにも、本校においては全校的な取り組みとして、定期的な校内の大掃除、校舎外のクリーン(除草)活動と第1学年に おいては職業調べ,第2学年の職場体験学習を実施する。
(3) 生徒指導・道徳指導の充実に努める
生徒指導についての共通理解と校内指導体制の確立
生徒指導部会を中心として全職員の共通理解を図ることを基本とする。
教師と生徒、生徒同士の好ましい人間関係の醸成
生徒指導については、その場の事象のみを捉えて、頭ごなしに叱るのではなく、本人の言い分を聞くことも大切である。そして、悪いことの本人の自覚をしっかり促せてから指導にあたることを基本としたい。
いじめ問題と不登校生徒解消への努力
いじめは、いじめられる者に原因があっても、いじめる側が絶対悪いという意識を確立させたい。それと同時に、生徒の危険信号としての言動には、安易に聞き流さず、即対応をお願いする。
登校生徒については、定期的な連絡を欠かさず、日常の生活振りをなどの情報収集や学校での出来事を学校だより・学年だよりなどを通じて情報提供に努めたい。
教育相談活動の充実
教育相談期間を通じて、全生徒とのコミニュケーションを図り、教師と生徒との人間関係を深め、個の生徒の特性や生活環境の把握に努めたい。
併せて、教科担当教師やスクールカウンセラーとの相互連携については、臨機応変に対応をお願いするとともに、保護者との教育相談についても門戸を開き、年間を通じて行う。
道徳指導の充実
学習指導要領総則2の一般方針に準じて実施されるものであり、人間は一人の考えや思いだけで何も出来ない。よって、人間相互の助け合いが必要性を認識させるとともに、人権尊重を基本として、義理や人情等の「心の教育」も育みたいと考える。
- 思いやりある人格形成と「心の教育」の充実
- 豊かな人間関係を育む道徳教育の深化
- 基本的人権を尊重する精神の涵養
(4) 健康・安全・給食指導の充実
保健意識の高揚と望ましい健康生活の習慣化
自分自身の身体の管理は自分でしっかり把握させ、調子の悪いときはどのように対応するべきなのか等の判断力を身につけさせる。特に、内服薬は与えていないので理解をさせたい。
安全指導の計画的実施と安全管理の徹底
生徒には、このような行動をすると安全性が損なわれるという危機意識を育むと同時に、職員間での連携を図り、安全対策を講じる。
給食指導の充実と好ましい食習慣の定着化
朝食抜き、孤立した食事(孤食)による気力の減退、さらには、カルシウム不足や脂肪の過剰摂取等の偏った栄養摂取や肥満症等の生活習慣病等、食に起因する健康問題について、正しい理解と望ましい習慣が身に付けられるよう、あらゆる機会を通じて指導するよう心がけてもらいたい。
(5) 豊かな教育環境の整備に努める
◆「環境は人をつくる」と言われます。環境には人的環境・物的環境に2分されますが、人的活動をなくしては出来得ません。「蟻の穴から堤も崩れる」のことわざにもあるように、ほおっておくとその被害も拡大します。そうすると、この学校はこれでいいんだという意識を植え付けてしまいます。校舎内外の環境について、生徒の意識改革を図る必要がある。そのために、職員の積極的な発想の転換をお願いします。
◆「師弟同行」の姿勢を基本とした清掃活動を展開し、勤労の精神・責任感・協力する態度を育てる。また、清掃用具の破損・不足などについては、適宜補充し、清掃活動に支障のないように気配りをお願いすると同時に、点検活動についても配慮をしてもらいたい。
(教師の活動と生徒の活動の連携)
◆古い掲示物の撤去や必要のない文書、廃棄した消耗品・備品等は放置することなく適宜手続きをとって処理に努めてもらいたい。
(6) 開かれた学校づくりの推進
家庭や地域及び関係機関との連携醸成
学校教育活動に対して一層の協力・理解を得るために、PTA活動・学校評議員・学校評価などを通じて保護者及び地域住民等の意見を取り入れていく。
積極的な情報の発信
学校だよりや学年だより及び保護者会などを通じて情報の提供に努める。
学習活動などへの地域社会の人材・素材の導入推進
生徒の意欲を換気し、学習活動の活性化のために、学校教育を理解し、積極的な協力者がいる場合、或いは職員からの強い希望がある時は、積極的な推進を図っていきたい。
(7) 報告・連絡・相談を密にし、協働の精神に努める
職員間での情報の共有化に努める。
校内における文書の進行管理やその処理状況を把握するため、文書管理規定の認識を高めるとともに意識の高揚に努める。
※ 校章の制定
開校直後、校章図案を公募し、当時の2年生男子の作品を採用した。校章は次のような意味をもっています。ペンは学習を、まわりの台座は堅固な土台を表します。そして、これら三つを組合せてあるのは「前原」「中野木」「前原団地」の三つの地域がしっかりと手を取り合っていくことを表しています。
校章の由来
