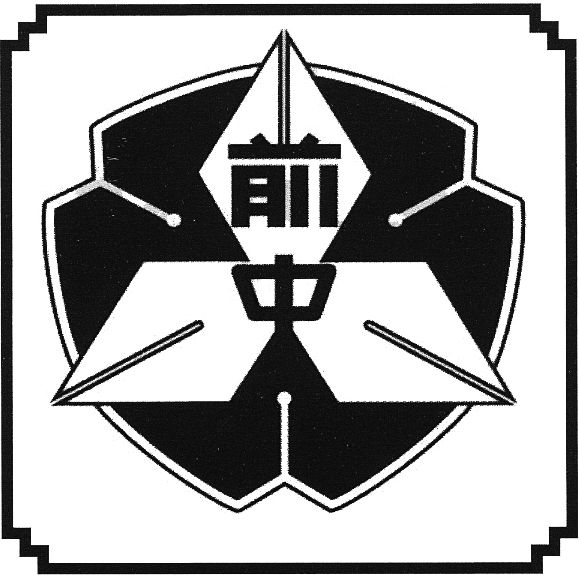 船橋市立
前原中学校
船橋市立
前原中学校
- 〒274-0826千葉県船橋市中野木2-33-1
- 047-478-6831
学校給食の沿革
我が国の学校給食は,明治22年10月,山形県鶴岡町(現鶴岡市)の私立忠愛小学校で,仏教各派連合により貧困児童を対象に昼食の供与を行ったのが起源である。
大正期の栄養補給的学校給食を経,昭和に入って,就学的配慮からの学校給食へと発展,更に戦時下における学校給食へと移行する中から,漸次,その対象の一般化及び実施主体の公共化という変遷をしてきた。
| 年月日 | できごと |
|---|---|
| 昭和21年12月11日 | 文部、厚生、農林三省次官通達「学校給食実施の普及奨励にっいて」が発せられ、戦後の新しい学校給食を開始する方針が定まった。 |
| 昭和21年12月24日 | 千葉、東京、神奈川三都県で25万人に対し、試験給食が開始された。 |
| 昭和22年 | 船橋市の船橋、宮本、海神、葛飾、八栄、高根、法典、塚田、三咲の9小学校で湯沸室や用務員室を調理場として、学校給食が開始された。 |
| 昭和27年3月 | 文部事務次官通達「昭和27年度の学校給食実施方針」が出され、この中で「学校給食は、教育計画の一環として実施する。」ことが、初めて明らかにされた。 |
| 昭和29年6月 | 第19国会で「学校給食法」が成立、公布された。以後、同年中に学校給食法施行令、施行規則、実施基準等が定められ、学校給食の実施体制が法的に整った。 |
| 昭和31年3月 | 「学校給食法」が一部改正され同法が中学校にも適用され、要・準要保護生徒に対する給食費補助が規定された。 |
| 昭和33年10月 | 文部省告示をもって、学習指導要領が定められ、学校給食が初めて「特別教育活動」の「学校行事等」の中に位置づけられた。 |
| 昭和35年 | 船橋市の小学校給食の普及率が94%に達し千葉県で1位となった。 |
| 昭和38年 | 船橋市の全小学校に学校栄養職員が配置された。船橋市の全中学校でミルク給食が開始された。 |
| 昭和39年 | 船橋市の全小学校で完全給食が開始された。 |
| 昭和40年 | 豊富中学校は、隣接する豊富小学校で調理したものを搬送する方法で完全給食が開始された。 |
| 昭和40年 | 給食調理員が、船橋市の職員として採用された。 |
| 昭和44年4月 | 中学校学習指導要領が改訂され、学校給食は、「特別活動」の「学級指導」に位置づけられた。 |
| 昭和51年4月 | 学校給食制度上に米飯給食が正式に導入され、学校給食用米穀の値引き率を35%とした。 |
| 昭和54年4月 | 学校給食用米穀の値引き率が最高70%となった。 |
| 昭和61年3月 | 日本体育・学校健康センター設立。学校給食実施基準の改訂に伴い、体育局通知「学校給食の食事内容について」が出され、新しい標準食品構成が示された。体育局長通知「学校栄養職員の職務内容について」が出された。 |
| 昭和61年4月 | 臨時教育審議会から教育改革に関する第2次答申が出され、家庭の教育力の活性化等を図る観点から学校給食を通じた学校、家庭、地域の連携の必要性が指摘された。 |
| 昭和62年4月 | 臨時教育審議会から教育改革に関する第3次答申が出され、教育財政の合理化、効率化の観点から学校給食業務における運営の合理化の一層の推進が求められた。 |
| 昭和63年7月 | 文部省は、学校保健課と学校給食課を統合し、学校健康教育課を設置した。 |
| 平成元年3月 | 中学校学習指導要領が改訂され、学校給食は、「特別活動」の「学級活動」に位置づけられた。 |
| 平成元年7月 | 船橋市保健衛生健康管理課内に学校給食準備室が設置され中学校給食の検討を始めた。 |
| 平成4年 | 法田、高根、習志野台の中学校に給食施設が建設された。 |
| 平成5年 5月 | 上記3中学校で選択方式による給食が開始された。 |
| 平成10年3月 | 本校前原中学校に給食施設が完成した。 |
| 平成10年5月 |
本校で、学校給食が開始された。献立は、A・B・弁当の選択制になった。 |
<参考文献> 船橋市中学校給食指導資料(平成7年4月1日改訂版)
船橋市教育委員会 学校教育部保健体育課 作成 より
